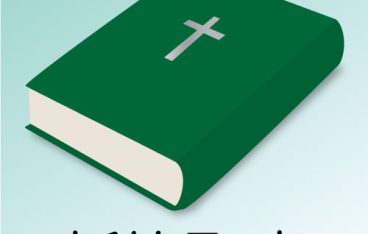2023年9月17日(主日)
主日礼拝『 年長者祝福 』
ローマの信徒への手紙 7章7~25節
牧師 常廣澄子
私達は今朝もこうしてご一緒に主なる神を礼拝するために集まっています。真の神を信じる者とされ、日々その神に導かれ、助けられ、守られて過ごせることを心から感謝したいと思います。ところで、このような恵み豊かな信仰の旅路を歩んでいる私達ですけれども、神を信じる者の生活がいつも平安と喜びで満たされているとは限りません。
今司会者の方に読んでいただきましたが、今朝与えられた7章の御言葉には「内在する罪の問題」という恐ろしい題がついていて、霊的なものと肉的なものについて書かれています。肉というのは私達が持っているこの体であり、それぞれの人間が持っている自我ともいえるでしょうし、霊というのは神につながる関係と言っても良いかもしれません。この二つはなかなか一致し難いもので、あらゆる時代のあらゆる人が、神を信じる者としてこの両者の間で悩んでいるのです。
パウロはここで何を語っているのでしょうか。パウロは人間が持つ一般的な本性を論じようとしたのではありません。自分自身を例として、たとえ神を信じる者であっても人間という者がどんなに頑なで弱い存在であるかを語っているのです。これはパウロだけの問題ではありません。あらゆるキリスト者の中に生じる共通の悩みであり、信仰者の誰もが経験する悩みだと思います。そしてパウロは、自分が悩んでいることの発端が律法にあることを指摘しています。
「(7-11節)では、どういうことになるのか。律法は罪であろうか。決してそうではない。しかし、律法によらなければ、わたしは罪を知らなかったでしょう。たとえば、律法が『むさぼるな』と言わなかったら、わたしはむさぼりを知らなかったでしょう。ところが、罪は掟によって機会を得、あらゆる種類のむさぼりをわたしの内に起こしました。律法がなければ罪は死んでいるのです。わたしは、かつては律法とかかわりなく生きていました。しかし、掟が登場したとき、罪が生き返って、わたしは死にました。そして、命をもたらすはずの掟が、死に導くものであることが分かりました。罪は掟によって機会を得、わたしを欺き、そして、掟によってわたしを殺してしまったのです。」
ここでパウロは、律法というものが、どうして人間の内に争いを引き起こすのかを明らかにしています。実際、律法や道徳というものが現れるまでは、人間は罪を意識していませんでした。たとえ罪を犯したとしても、それを罪とは思わなかったのです。けれども「~してはならない」という道徳律が入ってくると、人間はそれを守っていないこと、あるいはそれを守れないことに気づいて、自分の罪を自覚し始めるのです。たとえば7節にあるように「むさぼるな(人のものを欲しがるな)」と言われると、「どうして欲しがってはいけないのか、あの人が持っているあの素敵な物を自分も欲しい」という思いが起こって来て、それまで眠っていたむさぼりの心が呼び覚まされてくるのだ、というのです。そこで、罪を犯させないようにとして与えられた律法が、かえって罪を誘い出すような働きをすることになっていると語っているのです。
よくあることですが、小さな子どもは、自分が何かやってはいけないようなことをすると、周囲の大人が「あらあらそんなことしたらダメ」と困った様子を見せることに気づきます。それを面白がって、止めるのではなくて反対にさらに続けて悪さをしたりします。ダメだと言われることをするのは楽しいのです。このように「~してはいけない」という禁止命令がかえって罪を誘発するということは、身近にたくさんあります。
ほったらかしに育てられている子どもや、法律や道徳律がまだ整っていない国に住んでいる人達はたぶん罪を知らないでしょう。彼らは自然体で本能のままに生活しています。しかし、そのうちに「うそをついてはいけません、友達とけんかしてはいけません」と教えられる時がきます。それによって彼らは何が悪いことかを知っていくのです。けれども、それを知ったとしても止められません。むしろそういうことをしてはいけない、それは悪いことだと言われると、いっそうしてみたくなるものです。以前には悪いとは知らずに平気でしていたことを、それが悪いことだと知った後にもあえてするようになります。つまり道徳律によって善悪を知ると同時に、自分の中に潜んでいた罪の性質があらわになってきて、自分が罪人であることがわかってくるのです。「(9-10節)わたしは、かつては律法とかかわりなく生きていました。しかし、掟が登場したとき、罪が生き返って、わたしは死にました。そして、命をもたらすはずの掟が、死に導くものであることが分かりました。」
本来、律法とか戒めは、私達が命を全うするため、すなわち私達が神の御心に添った生活をするために与えられたものでした。ところが結果的にはそれらは私達が罪人であることを自覚させたにすぎないのです。善悪を知るということは、私達を善人にしないどころか、かえって私達の罪悪感をいっそう深くしました。現代の知性ある人達の中で、高慢やねたみや虚栄心や情欲等の心が悪いものであるということを知らない人がいるでしょうか。しかし人間はそれらがいかに悪い心であるかを知っていたとしても、それらに打ち勝つことができないのです。ことごとく分かっていながら、それらに負け、それらのとりこになっているのです。最近も大麻を吸ったことで逮捕された芸能人の話題がありました。悪いことだと分かっていても止められないのです。
そこで一つの考えが生じます。それは律法とか道徳とかいうようなものがあることが、そもそも問題のもとなのだから、そういうものさえなければ、人間は罪悪感を抱くこともないし、罪の意識を持つこともなく、自由に生きていくことができるのではないか、という考えです。その結果、律法そのもの、つまり律法があることを非難して、自分の罪を律法のせいにするかもしれません。そのような考え方に対して、パウロは言うのです。「(12-14節)こういうわけで、律法は聖なるものであり、掟も聖であり、正しく、そして善いものなのです。それでは、善いものがわたしにとって死をもたらすものとなったのだろうか。決してそうではない。実は、罪がその正体を現すために、善いものを通してわたしに死をもたらしたのです。このようにして、罪は限りなく邪悪なものであることが、掟を通して示されたのでした。わたしたちは、律法が霊的なものであると知っています。しかし、わたしは肉の人であり、罪に売り渡されています。」
霊と肉の分裂の原因が律法にあるといえば、いかにも律法そのものが悪いように思われるかもしれませんが、実際はそうではありません。「律法は聖なるものであって、正しく、そして善なるものである」とあるように、モーセの律法をはじめとして、あらゆる道徳律は、直接、間接、神のみ旨によって私達人間に与えられたものです。それでは、なぜ聖なるものであって正しい律法が私達の内に罪を誘発するのでしょうか。それは、もともと私達の内にある罪が律法によって照らし出されて、表面に現われてくるからです。暗い部屋の中にいると、そこにほこりがあることがわかりませんが、そこに日光が射し込むとほこりがあるのがわかります。これを、日光が射し込むからほこりが出るのだと言って日光を責めたらどうでしょうか。悪いのは日光ではなく部屋そのものです。それと同じ様に、悪いのは律法そのものではなく私達自身なのです。律法はただ私達の罪を明るみに持ち出し、それが罪であることを現わす機会となったにすぎません。
「(14節)わたしたちは、律法が霊的なものであると知っています。しかし、わたしは肉の人であり、罪に売り渡されています。」律法と言うと、私達はそれを外面的、形式的なものとして受け取ります。しかし、律法は本来「霊的なもの」であり、私達の霊に関係している内面的、精神的なものなのです。従って律法を守る場合には、その精神を理解して、それを心から守らなければ、真に守ったとは言えません。それに反して、私達人間は「肉につけるもの」ですから、自然のままでは肉体的、本能的に生きています。「罪に売り渡されている」というのは、すべての人が罪という主人のもとで、その支配下に置かれているということです。
そこで次に私達を支配している罪とは何かということを考えてみましょう。パウロは罪を定義したり、説明したりしないで、その実態を自分の経験を通して生き生きと描き出しています。「(15-23節)わたしは、自分のしていることが分かりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。もし、望まないことを行っているとすれば、律法を善いものとして認めているわけになります。そして、そういうことを行っているのは、もはやわたしではなく、わたしの中に住んでいる罪なのです。わたしは、自分の内には、つまりわたしの肉には、善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意志はありますが、それを実行できないからです。わたしは自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。もし、わたしが望まないことをしているとすれば、それをしているのは、もはやわたしではなく、わたしの中に住んでいる罪なのです。それで、善をなそうと思う自分には、いつも悪が付きまとっているという法則に気づきます。『内なる人』としては神の律法を喜んでいますが、わたしの五体にはもう一つの法則があって心の法則と戦い、わたしを、五体の内にある罪の法則のとりこにしているのが分かります。」
ここに、罪の実体がきわめてわかりやすく表現されています。それを一口に言うならば、罪とは、こういうことをしたいと思いながらそれをしないで、こういうことをしたくないと思いながらそれをすることです。私達の内には、善を欲する霊的な心と、悪にひかれる肉的な心とがあります。これら二つが対立した時、悪に引かれる傾向が善を欲する心に打ち勝って、肉的な心が霊的な心を支配してしまうこと、これが罪なのです。「(22-23節)『内なる人』としては神の律法を喜んでいますが、わたしの五体にはもう一つの法則があって心の法則と戦い、わたしを、五体の内にある罪の法則のとりこにしているのが分かります。」人の心の中は霊と肉との戦いの場であって、まじめであればあるほどその戦いは激しくなります。そしてどちらが勝つかと言えば、肉が勝利を得ることの方が多いのです。これが私達の魂の真相です。
ここにおいてパウロの悩みは頂点に達し、悲痛な叫びとなります。「(24節)わたしはなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から、だれがわたしを救ってくれるでしょうか。」ここで「死に定められた体」とは、罪のために必然的に死に至る者という意味です。そのような惨めなものを救ってくださるお方はいないであろうかと、パウロは叫んでいるのです。
パウロは律法に誘発されて霊と肉の戦いを経験し、その極限において自分に自分を救う力がないことを痛感しました。そして自分を越えたお方に目を向けました。もし彼がここで「自分を救う者は結局自分以外に無い」と考えたならば、彼は再び律法主義に陥り、自力で善を行おうとして空しい努力を重ねることになったでしょう。また、「自分を救う者はこの世にだれもいない」と諦めたな
らば、彼は虚無主義に陥って救いのない世界の中に生きたかもしれません。しかし、彼はそのどちらにも引き込まれずに正しい一点に目を向けたのです。それがイエス・キリストです。
「(25節前半)わたしたちの主イエス・キリストを通して神に感謝いたします。」パウロは晴れやかに告白しています。このお方こそ、私たちを悩みから救い、死の体から解き放つ方です。イエス・キリストは、神が人となってこの世に現われ、人の罪のために苦しみ、その贖いとして十字架にかかり、死んでよみがえったお方です。このお方を仰ぐ時、私達の罪や絶望は解決され、悩みは感謝に、不安は平安に変えられるのです。従ってこのお方から目を離して自分自身や周囲のものを見て惑わされるなら、私達は再び分裂と闘いとの世界に追いやられてしまいます。ですから、私達の成すべきことはただ一つ、キリストから目を離さないようにすることです。「(25節後半)このように、わたし自身は心では神の律法に仕えていますが、肉では罪の法則に仕えているのです。」
このように、神を信じて真剣に御言葉を受け止めて生きていこうとする人は、必ず霊と肉との戦いを経験します。肉体をもってこの世に生きている限り、信仰者はこの戦いを免れることはできないばかりか、むしろ、この戦いのあることが信仰に生きている証拠だといえるのかもしれません。私達が救われた後にもなお霊と肉の分裂や戦いが続くのは、その都度私達が自分の弱さを知ってキリストを仰ぎ、その恵みを受けるためだと思います。キリストに救われた者には、霊と肉との戦いすらも神に近づく道となり、一切のものが共に働いて益となることを心から感謝したいと思います。
(牧師 常廣澄子)