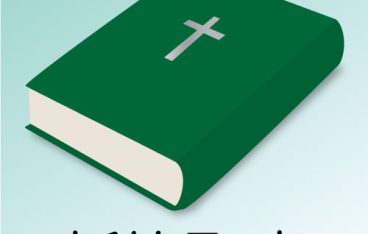2025年6月15日(主日)
主日礼拝
コリントの信徒への手紙 一 16章1~12節
牧師 常廣 澄子
コリントの信徒への手紙一の最後の章になりました。パウロの長い手紙もいよいよ終わりです。パウロはここまでずっと、コリントの教会からの質問に答えながら、ある時は警告を発し、ある時は勧めをなし、いろいろと教えを説いてきました。このあたりでだいたい語るべきことを語ってきたようで、そろそろ締め括りに入ろうとして、幾つか事務的な事に触れています。15章でのパウロは、息もつかせぬような見事な復活賛歌を語って読む者を感動させましたが、この16章では、交響曲の終楽章のように静かに語っています。
まず16章の始めの部分では募金のことが書かれていますが、これは、その前の15章58節「わたしの愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の業に常に励みなさい。主に結ばれているならば自分たちの苦労が決して無駄にならないことを、あなたがたは知っているはずです。」このみ言葉の具体的な実践、その実例として考えることができます。
16章全体を見てみますと、まず1-4節に「聖なる者たちへの募金」について、次の5-9節には「パウロの伝道旅行の計画」について書かれています。その後にはテモテやアポロ、ステファナやフォルトナト、アカイコ、アキラ、プリスカなど人の名前がたくさん出てきて、人事に関することが書かれています。そしてその後で挨拶と奨励があり、終わりの祈りで閉じられています。本日はその前半部分から聞いていきたいと思います。
パウロはまず募金について語ります。これもコリント教会からの質問があって答えたもののようです。「16:1 聖なる者たちのための募金については、わたしがガラテヤの諸教会に指示したように、あなたがたも実行しなさい。」ここにある「聖なる者たちのための募金」というのは、エルサレムにある教会の貧しい信徒たちを助ける献金のことです。「聖なる者」と書かれているのは、キリストのために聖別された者という意味で、キリスト信者のことです。ユダヤ全土に大きな飢饉があったため、エルサレム教会の貧しい信徒たちの生活は大変困窮していました。パウロは彼らを助けることは全教会の責任だと感じていたのです。それでパウロは各地で福音を語りながら、方々の教会でそのことを伝えて援助を依頼しました。「ガラテヤの諸教会に指示したように」というのはそのことです。パウロはややもするとバラバラになってしまいそうな異邦人教会とユダヤ人教会を「愛の絆」で結ぼうとしているのです。その依頼がコリント教会にも届いていたのです。
「16:2 わたしがそちらに着いてから初めて募金が行われることのないように、週の初めの日にはいつも、各自収入に応じて、幾らかずつでも手もとに取って置きなさい。」この「週の初めの日」というのはもちろん日曜日のことです。キリストを信じる者たちは、キリストの復活を覚える日曜日に、共に集って礼拝を捧げるようになっていました。日曜日は週の初めの日であり、神に聖別された日です。現代に生きる私たちもそのような心で過ごすべき日であります。
この募金(献金)に対して、パウロは極めて周到な注意を与えています。たぶんコリントだけでなく、他の教会にも同じことを語っていたのだろうと思います。「各自収入に応じて」とは、一度にまとめてお金を出すのではなく、日曜日ごとに、貧しい人も富める人も無理のないように自分の収入に応じて、募金するお金を取り分けておきなさいということです。そのように前もって少しずつ蓄えておけば、パウロが来た時にあわててみんなからお金を集めるという事態が生じません。細かい指示かもしれませんが、これは教会から教会への愛の献金なのです。前もって少しずつ集めるのは、その行為と共に相手を思う気持ちと祈りも伴っているということです。私たちも毎年いろいろな災害に遭って被災した教会やその地域の方々のために募金を集めて送りますが、このような細かい愛の心遣いを持っていたいと思います。
そしてそのようにして集められた愛の献金は、パウロがそちらに行った時に、あなた方から承認された人たち(教会が適当と選んだ人たち)に持たせ、これに手紙を添えてエルサレムに届けに行かせようと言っています。「16:3 そちらに着いたら、あなたがたから承認された人たちに手紙を持たせて、その贈り物を届けにエルサレムに行かせましょう。」しかし当時、ギリシアのコリントからユダヤのエルサレムに行くのは大変困難な旅でした。しかし困っている教会を助けるためにはどうしても必要で大切なことでした。それはただの助け合いというだけでなく、キリストの愛に基づく働きだったからです。募金する人も募金を届ける人もキリストの愛によって動かされているのです。そして究極的には、助けを必要としている人たちへの捧げものは、神に対する供え物であることをも示唆しています。すべてのものは神から与えられたものだからです。
パウロは、もしコリント教会がそのことを良しとするなら、自分も一緒にエルサレム教会に行ってもいいですよと、語っています。「16:4 わたしも行く方がよければ、その人たちはわたしと一緒に行くことになるでしょう。」コリント教会とエルサレム教会とが、主にあってさらに親密さを増していくために、自分が何か役に立つのであれば、パウロにとって困難な旅など問題ではないのです。
パウロはここで、マケドニアを経由してコリントを訪問したいという計画を告げています。「16:5 わたしは、マケドニア経由でそちらへ行きます。マケドニア州を通りますから、16:6 たぶんあなたがたのところに滞在し、場合によっては、冬を越すことになるかもしれません。そうなれば、次にどこに出かけるにしろ、あなたがたから送り出してもらえるでしょう。」このことは使徒言行録20章を読むと、実現されていることがわかります。
ここには、マケドニアは通過するだけ(滞在しない)のように書かれています。その理由は、マケドニアにある幾つかの教会は小さな教会が多く、それらの教会には特に問題がなかったからだと考えられます。「あなたがたのところに滞在し」というように、コリントに滞在することに言及しているのは、コリント教会が大きくてその力があったからだと思われます。ここにはコリント教会の人たちに格別な親しみを感じているパウロの気持ちが読み取れます。
「場合によっては、冬を越すことになるかもしれません」と書かれているのは、冬は季節風の関係で航海が困難だったからでしょう。とにかくパウロはコリントに行ったらそこでゆっくりしたいという希望を持っていたようです。コリント教会の人たちと膝を交えて主への信仰を語り、またいろいろな問題について話し合いたいと思っていたのでしょう。
そして「次にどこに出かけるにしろ、あなたがたから送り出してもらえる」と言っています。パウロはこの時、コリントの次にどこへ行くことを考えていたのでしょうか。パウロがいつかローマに行こうという遠大な計画を持っていたことは使徒言行録の19章21節からわかりますが、たとえその行く先がどこであろうと、有力なコリント教会の人々の祈りと援助をパウロは期待していたのでしょう。そういうこともあり、コリント教会ではゆっくりと落ち着いて話し合いたかったのです。それが7節にはっきり書かれています。
「16:7 わたしは、今、旅のついでにあなたがたに会うようなことはしたくない。主が許してくだされば、しばらくあなたがたのところに滞在したいと思っています。」コリント教会の人たちは、今すぐにでも来て欲しいと思っていたかもしれませんが、パウロは、あわただしい旅をして、そのついでに訪問するというようなことはしたくなかったのです。パウロはコリントへはゆっくり落ち着いた訪問がしたかったし、できればしばらく滞在したかったのです。しかし何事も神のみ旨次第ですから、主のお許しがあれば実現するでしょうと語っています。
「16:8 しかし、五旬祭まではエフェソに滞在します。16:9 わたしの働きのために大きな門が開かれているだけでなく、反対者もたくさんいるからです。」パウロは今エフェソでこの手紙を書いています。「五旬祭」というのは、先日のペンテコステ(聖霊降臨)礼拝で永田先生の説教を通してその説明をお聞きになったと思いますが、過ぎ越し祭から五十日目にあたる日で(大体現在の五月から六月頃)、その季節にユダヤのお祭りがありました。パウロはこの五旬祭まではどうしてもエフェソに滞在していると言っています。
それは、彼がエフェソにいる間に、伝道の門戸が大きく開かれたからだと言います。しかしこのことが具体的にどのようなことであったのか、使徒言行録を読んでもはっきりわかりません。しかしとにかく伝道のための大きな機会が与えられたようです。しかし、一旦伝道の門戸が開かれると、他方ではそれに反対する者たちも起こってきます。それがいろんな人がいる人間世界です。今の時代もそうですが、当時においても、罪の赦しの福音はなかなか受け入れられないものだったようです。伝道する時はそれに反対する人たちがいることを覚悟していなければなりません。ともあれ、エフェソは偶像の神々に囲まれた迷信の盛んな都市でした。パウロがエフェソで多くの人々の反対にあったことが使徒言行録19章に書かれています。そのような諸々の事情によって、パウロは今すぐにはコリントに行けなかったようです。
「16:10 テモテがそちらに着いたら、あなたがたのところで心配なく過ごせるようお世話ください。わたしと同様、彼は主の仕事をしているのです。16:11 だれも彼をないがしろにしてはならない。わたしのところに来るときには、安心して来られるように送り出してください。わたしは、彼が兄弟たちと一緒に来るのを、待っているのです。」パウロはエフェソに留まっていて、そこからテモテとエラストを送り出したようです。使徒言行録19章22節を見ると、「そして、自分に仕えている者の中から、テモテとエラストの二人をマケドニア州に送り出し、彼自身はしばらくアジア州にとどまっていた。」とありますから、この二人はマケドニアの諸教会を訪れて、できたらコリント教会を訪問する予定だったのかもしれません。
この手紙はテモテがコリントに到着する前にコリント教会に届くように書かれています。それで、「もしテモテがそちらに着いたら、心配なく過ごせるように世話してやって欲しい」つまり彼に良くしてやって欲しいと頼んでいるのです。しかし、テモテたちがコリント教会に来たかのかどうかは、コリントの信徒への手紙二を見ても、その他の手紙類を見ても、その事については明らかではありません。もしかしたら、何らかの事情で来られなかったのではないかと考えられます。
テモテの派遣については、この手紙の4章17節にも書いてありますし、フィリピの信徒への手紙2章19-22節には、テモテが確かな人物であり、優しい愛の伝道者であると書かれています。しかし何分にも年が若いのです。ですから経験も十分ではありません。もしかしたらコリント教会の中にはそんなテモテに対して、彼を侮辱したり軽蔑するような人がいるかもしれません。それを考えるとパウロは心配なのです。パウロの心は父親のように、愛する弟子を思いやり、案ずる気持ちでいっぱいです。ですから「だれも彼をないがしろにしてはならない」と言い、自分のところに戻って来る時は「安心して来られるように送り出してほしい」と頼んでいるのです。パウロは自分自身が孤独や不安の中にいるにもかかわらず、テモテを思う優しい心を思うと感動します。
その後にはアポロが出てきます。「16:12 兄弟アポロについては、兄弟たちと一緒にあなたがたのところに行くようにと、しきりに勧めたのですが、彼は今行く意志は全くありません。良い機会が来れば、行くことでしょう。」この手紙の1章には、コリント教会の中に、「わたしはパウロにつく」「わたしはアポロに」「わたしはケファに」「わたしはキリストに」などと言い合って分派ができていたことが書かれていました。パウロは心を痛めて教会の一致を勧めたわけですが、コリント教会には、アポロの雄弁さと博学のゆえに多くのファンがいたようです。それで彼らの中には、アポロにもう一度コリントに来てほしいという要望があったのかもしれません。
パウロはアポロに、「兄弟たち」(コリント教会からエフェソに来ていて近くコリントに帰ろうとしていた人たち)と一緒に是非コリントに行くように再三すすめたようですが、アポロは固辞して、コリントに行く気持ちがありませんでした。どうして彼は行きたくなかったのでしょうか。想像ですが、アポロはコリント教会の分派争いのことを今でも気にしていたのではないでしょうか。しかし後になって、自分が情熱を傾けて伝道した地がどうなっているか、懐かしさと共に行ってみたい気持ちになって、きっと良い機会にアポロはコリントを再訪したかもしれません。そうであって欲しいと私は願っています。
私は自分の生活で体験していることですが、不思議なことに、キリストへの信仰を通して知り合った人間関係は、何年たっても変わらずに続いていくのです。どんなに時間が経っていて、どんなに離れて暮らしていても、主にある交わりは変わらないのです。それは、年月や空間を越えて働いておられる主の御霊のなせる業だからであり、神につながっている家族だからだと心から感謝しております。