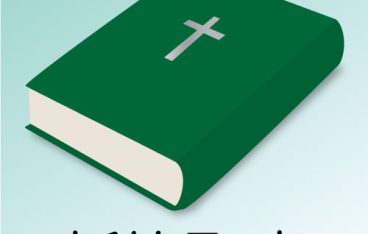2025年6月22日(主日)
主日礼拝
使徒言行録 12章1~19節
牧師 常廣 澄子
本日は19節までしかお読みしませんでしたが、実は12章1節から24節は、バルナバとサウロの旅行記事に挟まれた挿入文だと考えられます。それはまず11章29-30節で、アンテオケ教会からの援助の品をバルナバとサウロがエルサレムの長老たちに送り届けたことが書いてあり、12章25節で「バルナバとサウロはエルサレムのための任務を果たし、マルコと呼ばれるヨハネを連れて帰って行った。」と結んでいることからわかります。そして何よりもここには「12:24神の言葉はますます栄え、広がって行った。」とあり、アンテオケ教会の発展に負けず劣らず、エルサレム教会においても、神の言葉が立派に前進していったことが書かれているのです。ではその力はどこから来ているのでしょうか。その一つの出来事として、ペトロの投獄とそこからの脱出事件が書かれているのではないかと思います。
「12:1 そのころ、ヘロデ王は教会のある人々に迫害の手を伸ばし、12:2 ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。」1節にあるヘロデ王とは、イエスが生まれた頃のヘロデ大王の孫にあたるヘロデ・アグリッパ1世です。ヘロデ大王の死後、その領地は三人の息子たちに分割されましたが、この三人は死んだり位を退けられたりして次々と失脚したので、それらの土地をすべてもらい受けて全ユダヤの王となりました。彼はなかなか人心をつかむのが巧みで、ユダヤ教の儀式にも熱心でしたので、ファリサイ派の人たちからも慕われていました。彼はまず使徒ヤコブを剣で殺しました。「12:3 そして、それがユダヤ人に喜ばれるのを見て、更にペトロをも捕らえようとした。」いかにもユダヤ人に気に入りそうなやり方です。「12:3それは、除酵祭の時期であった。 12:4 ヘロデはペトロを捕らえて牢に入れ、四人一組の兵士四組に引き渡して監視させた。過越祭の後で民衆の前に引き出すつもりであった。」
ヘロデは、ユダヤ中から敬虔な信者が集まって来る過越祭の時期をねらって、その祭りの後で、捕えたペトロを民衆の前に引き出す考えでした。ペトロが牢から救出された時、「12:11 ペトロは我に返って言った。『今、初めて本当のことが分かった。主が天使を遣わして、ヘロデの手から、またユダヤ民衆のあらゆるもくろみから、わたしを救い出してくださったのだ。』」と言ったのはそのことです。キリストを信じる者たちは、今までのようにユダヤ教徒からの迫害だけでなく、ヘロデ王という強力な国家権力も加わった弾圧の下に置かれていたのです。
ヘロデに殺されたヤコブについてですが、主の弟子であったヤコブとヨハネの兄弟は、生前イエスから特別な預言を受けたことがありました。「確かに、あなたがたはわたしが飲む杯を飲み、わたしが受けるバプテスマを受けることになる。しかし、わたしの右や左にだれが座るかは、わたしが決めることではない。それは、定められた人々に赦されるのだ。」(マルコによる福音書10章39-40節)この預言の通りに、ヤコブは十二使徒の中で最初の殉教者となりました。一方の兄弟であるヨハネは生き延びて、愛に満ちた手紙「ヨハネの手紙」三通を書き、パトモス島に流されて黙示録を記しました。何という違いかと思いますがどちらも主の御心なのでしょう。寿命が長いか短いかは問題ではありません。生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。
ここには、ヤコブ殺害を契機として捕らえられたペトロの物語が書かれています。ペトロは、以前にも投獄されたことがありましたが、その時も主のみ使いによって救い出されました。しかし、今回はそれと比較にならないほどスケールが大きく、詳しい描写がなされています。
まず牢内でのペトロの警護は厳重を極めていました。ローマ軍の慣例を真似て「四人一組の兵士四組に引き渡して監視させた」のです。四人一組の兵士は、二人が牢の外を守り、二人が二本の鎖でペトロの左右に付き添っていました。もしかしたらヘロデは以前ペトロたちが牢を抜け出したことを聞いていたのかもしれませんが、ヘロデの用心深さは異常なくらいでした。その上、10節にあるように、第一、第二の衛兵所があり、その先に町に通じる鉄の門があったのです。ペトロは絶体絶命の状態でした。そのような状態で捕らわれていて、遂に6節にあるように、「ヘロデがペトロを引き出そうとしていた日の前夜」になってしまったのです。
ところがその最後の瞬間に奇蹟が起こりました。これはペトロ自身でさえ現実の事とは思われず、幻を見ているのだと思ったほどです。「12:9 それで、ペトロは外に出てついて行ったが、天使のしていることが現実のこととは思われなかった。幻を見ているのだと思った。」
では、その夜起こったことを見ていきましょう。「12:6 ヘロデがペトロを引き出そうとしていた日の前夜、ペトロは二本の鎖でつながれ、二人の兵士の間で眠っていた。番兵たちは戸口で牢を見張っていた。」ここまではいつもの通りです。「12:7 すると、主の天使がそばに立ち、光が牢の中を照らした。天使はペトロのわき腹をつついて起こし、『急いで起き上がりなさい』と言った。すると、鎖が彼の手から外れ落ちた。 12:8 天使が、『帯を締め、履物を履きなさい』と言ったので、ペトロはそのとおりにした。また天使は、『上着を着て、ついて来なさい』と言った。」ペトロは、まるで操り人形のように天使から手取り足取り指図を受け、それに従っています。
「12:9 それで、ペトロは外に出てついて行ったが、天使のしていることが現実のこととは思われなかった。幻を見ているのだと思った。12:10 第一、第二の衛兵所を過ぎ、町に通じる鉄の門の所まで来ると、門がひとりでに開いたので、そこを出て、ある通りを進んで行くと、急に天使は離れ去った。」天使は難なく牢の戸を開けて、二つの衛兵所を通り過ぎ、町に通じる鉄の門を開かせてペトロを外に出すと、その姿が見えなくなりました。それでペトロはやっと我に返り、主が天使を遣わしてペトロを助け出してくださったことがわかったのです。
こういう話を聞くと、現代人は誰もが首をかしげます。現代人の多くは天使の存在やその働きをあまり真剣に考えません。しかしキリストの救いを信じ、ペンテコステ(聖霊降臨)の出来事を信じる私たちは、霊的存在である天使をも造りだされる神のみ業を疑うことはありません。私たちもそれぞれの人生のある時期、無我夢中で突っ走ってきた後に、ふっと我に返って思った時があるのではないでしょうか。「今やっとわかった、あの難局を切り抜けられたのは主が助けてくださったからだ。」と。(あの砂の上の足跡の詩のように、私が大変だった時、主は私をおぶって歩いていてくださったのです。)もちろんそこに天使がいるのを見たわけではありません。しかし、信仰の目が開けて我に返る時、それを乗り越えられたのは自分の力ではなかったことに気づくのです。
ヘブライ人への手紙1章14節には「天使たちは皆、奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになっている人々に仕えるために、遣わされたのではなかったですか。」とあるように、天使は私たち神を信じる者たちに仕える霊です。ですから、後になって我に返ったペトロが、「12:11 今、初めて本当のことが分かった。主が天使を遣わして、ヘロデの手から、またユダヤ民衆のあらゆるもくろみから、わたしを救い出してくださったのだ。」と悟ることができたのです。
もう一つ、この脱獄物語が以前と違っていることは、そこに教会の祈りがあったことです。「12:5 こうして、ペトロは牢に入れられていた。教会では彼のために熱心な祈りが神にささげられていた。」
二人の番兵が戸口で牢を見張り、二人の兵士は二本の鎖でペトロの左右につながれています。この牢は町に通じる鉄の門を入って、第一第二の衛兵所を通ってその奥にあるのです。ペトロがその牢に入れられて、いよいよ明日は民衆の前に引き出されるという最後の夜のことです。その夜も大勢の信徒たちが(12節)マルコと呼ばれていたヨハネの母マリアの家に集まって祈っていたのです。
さて、天使によって牢から助け出されたペトロは、仲間のいるマリアの家にたどり着くと、その戸をたたきました。「12:13 門の戸をたたくと、ロデという女中が取り次ぎに出て来た。」ロデという女中は「12:14 ペトロの声だと分かると、喜びのあまり門を開けもしないで家に駆け込み、ペトロが門の前に立っていると告げた。」何としたことでしょう。ロデは門を開けることもせずに家の中に駆け込んでしまいました。その間、追手が迫って来るのを気遣いながらペトロは戸を叩き続けています。ペトロを放っておいて家に駆け込むとは何と気の利かぬ女中かと思うかもしれません。けれどもこれを書いた著者ルカは、これは彼女の「喜びのあまり」の行動だと、あたたかい目でこの時の様子を語っています。しかし、ペトロの救いと解放を祈り続けていた信徒たちが、いざペトロが救い出された現実に出くわした途端、驚き、疑い、取り乱してしまったのはいったいどうしたことでしょうか。
ここで、私たちは彼らが祈っていたことについて考えてみたいと思います。番兵たちは戸口で見張っている中、ペトロは二本の鎖でつながれて二人の兵士の間で眠っていたのです。ペトロの心は安らかです。天使が光で照らした後も、わき腹をつついて起こさないと気づかないくらいぐっすり熟睡していました。明日の運命をすっかり主に委ねている、これほどの信頼の大きさ、心の安らぎは教会で信徒たちが心を尽くして祈ること以外、に何によって得られるでしょうか。ペトロのための祈りは確かに聞かれていました。
しかし私たちはやはり、彼らがどんなにペトロの釈放を祈り願っていたとしても、祈りの成就を信じることなく祈っていたのではないかという印象を持ってしまいます。祈りの力を信じることなしに祈っていたと言われても仕方がありません。ロデが門を開けずに家の中に入って来たことは「喜びのあまり」の行為であると言われても、それは予期せぬ喜びだったからでしょう。どんなに熱心に祈っていたとしても、彼らはその祈りが叶えられることは期待していなかったように思えます。ロデが「ペトロが門の前に立っている」と告げると、「あなたは気が変になっているのだ」と言い、戸口に立っているペトロを「それはペトロを守る天使だろう」と言ったりしています。ここら辺の様子を考えてみると、どうみても彼らは疑いながら祈っていたように思えます。ですから、私たちはこの事件に言いようもない親近感を覚えるのではないでしょうか。現代の私たちと同じような弱さや不安感や疑いをもつ人たちがここにはいます。そして、そういう弱さを抱えた信徒たちの思いを越えて「主なる神が救い出してくださった」のです。主なる神の勝利です。
エフェソの信徒への手紙3章20節には、この神のことを「わたしたちの内に働く御力によって、わたしたちが求めたり、思ったりすることすべてを、はるかに超えてかなえることがおできになる方」というように書かれています。このような力ある神を信じるクリスチャンは、鉄の扉で閉じ込めたり、鎖でつなぐ者たちよりもはるかに強いのです。
「12:18 夜が明けると、兵士たちの間で、ペトロはいったいどうなったのだろうと、大騒ぎになった。12:19 ヘロデはペトロを捜しても見つからないので、番兵たちを取り調べたうえで死刑にするように命じ、ユダヤからカイサリアに下って、そこに滞在していた。」ヘロデは、この事件の始末を家来たちにとらせ、番兵を死刑にすることで責任を取らせました。それから自分はローマ帝国の行政上の中心地であるカイサリアに下っていきました。そこに滞在している時に不慮の死を遂げたのです。この後にヘロデがどのようにして死んだか、ヘロデの死について書かれています。
当時、地中海沿いにあるティルスとシドンの住民はユダヤから食料を買っていました。しかし、彼らはヘロデの不興を買っていたので何とかしてその機嫌を取りどしたいと願っていました。そこで、侍従ブラストを通して和解しようとしたのです。定められた日にヘロデが王の服を着て演説をすると、集まった人々が「神の声だ、人間の声ではない。」と叫びました。するとその時に主の天使がヘロデを撃ち倒しました。つまり、ヘロデは自分を神とした時に罰せられたというのです。ヘロデの死はユダヤの歴史家ヨセフスが書いた『ユダヤ古代史』にも書かれていますが、この使徒言行録の記事とは少し異なっています。どちらにせよ、神ならぬ人間が神のように崇め奉られて、有頂天になっている時に、蛆に食い荒らされて息絶えた、という惨めさこそが神の審きだといえるのではないでしょうか。
こうして、「12:24神の言葉はますます栄え、広がって行った。」これはヘロデという迫害者が死んでしまったから、教会が前進していったという意味ではありません。ペトロの奇蹟的救出やヘロデの死という審きを体験した教会が、この世のどのような権力をも超える大きな力を持つ主こそが自分たちを導く神であると確信した結果です。私たちは、神の前にある自分の罪を率直に認めて悔い改め、真の神にのみ栄光を帰すことによって、ほんとうの意味で福音が広まっていくのです。