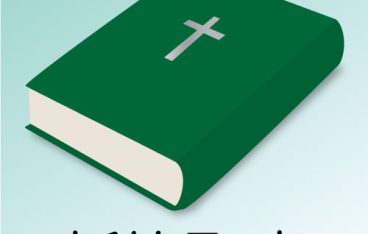2025年9月7日(主日)
主日礼拝『 主の晩餐 』
ルカによる福音書 18章15~17節
牧師 永田 邦夫
本日もルカによる福音書からのメッセージをご一緒にお聞きして参りましょう。
この箇所は、マタイによる福音書にもマルコによる福音書にも並行記事がありますので、必要に応じてその箇所も参考としていきましょう。
冒頭の15節には「イエスに触れていただくために、人々は乳飲み子までも連れて来た。弟子たちは、これを見て叱った。」とあります。ここに「乳飲み子」とある言葉は、先に挙げた二つの福音書では、いずれも「子供たち」と記されています。
いまここに起ころうとしている事は、人々が乳飲み子までも連れて来て、主イエスから祝福をいただこうとしている、実に微笑ましい出来事なのです。なのに、弟子たちは、これを見て叱った、とはどういうことなのでしょうか。そして、ここに何が起ころうとしているのでしょうか。
この事につきましては、聖書解説者(神学者)が次のように解釈しています。つまり、連れてこられたのが、乳飲み子であっても、子供であっても問題ではなく、主イエスが現在、エルサレムを目指して進んでおられる忙しい時期なので、出来るだけ主イエスの手を煩わせないようにしよう、という弟子たちの気配りから起こった出来事ではないだろうかということです。
ルカによる福音書では、この直後に、主イエスが乳飲み子を呼び寄せて祝福し、続いて、神の国についての教えへと進んでおり、この箇所を読む人に感動を与えております。
主イエスは、私たち一人ひとりの存在を、そしてその命を大切にしてくださる方です。わたしたちが、やれ乳飲み子だ、子供だ、とあれこれ言っておりますが、御子イエスが人としてこの地上に来られてから、人間一人ひとりを、本当に大切にしてくださいました。このことにつきましては、これ以上、なんの説明も要りません。
次の16節に入ります。「しかし、イエスは乳飲み子たちを呼び寄せて言われました。『子供たちをわたしのところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。』」とあります。
ここにも主イエスが、わたしたち一人ひとりの尊い命の尊厳を重んじておられる様子がわかります。
この16節の最後の部分、「神の国はこのような者たちのものである。」を説明している二つの独自記事が本日箇所の直前に置かれていますので、順番に見ていきましょう。
一つ目の記事は、18章1節~8節の「やもめと裁判官」のたとえです。
1節には「イエスは、気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために、弟子たちにたとえを話された。」とあります。
その概要を確認していきましょう。
ある町に神を畏れず人を人とも思わない裁判官がいた。そしてこの裁判官には、ひっきりなしにやって来ては、裁判を頼みこむやもめの人がいて、その裁判官をほとほと困らせていたというのです。
イエスは弟子たちに対して、「よく聞いておきなさい。神は、昼も夜も叫び求めている、神の民イスラエルに対して、その悩みや苦しみをいつまでも放っておかれるはずがない。速やかにその悩み苦しみを裁いてくださる。」と教えておられます。
わたしたち人間は、自分中心に物事を考え、あの人はうるさいとか、とやかく言いますが、神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たち(これは本来はイスラエルの民のことを言います。)すなわち、神を信じて従って来るすべての人々を、神は速やかに裁いてくださるのだと教えておられるのです。
二つ目の記事は18章9節~14節の「ファリサイ派の人と徴税人」のたとえです。
9節からイエスは、自分は正しい人間だとうぬぼれて、他人を見下している人々に対して、たとえによって話されました。
10節「二人の人が、祈るために神殿に上った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。」とあります。11節「ファリサイ派の人は立って(神殿の前の方でしょう)心の中でこのように祈った。『神様、わたしはほかの人たちのように、奪い取る者、不正な者、姦通を犯す者でなく、また、この徴税人のような者でもないことを感謝します。」とあります。
もう一人の徴税人は、13節「遠くに立って、目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。「神様、罪人のわたしを憐れんでください。」とです。
この二人の祈りに対して、主イエスの言葉が14節にあります。「言っておくが、義とされて家に帰ったのは、この人であって、あのファリサイ派の人ではない。だれでも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。」と言われました。
考えてみますと、ファリサイ派のファリサイとは「分離された者」という意味です。もともとユダヤ教の人々が、自分たちは神から与えられた律法をしっかり守り、そのように生きている者であると自負して、自分たちを律法を守れない汚れた人たちとは違うのだという意味でファリサイ人と呼んでいたのです。
しかしこのたとえでは、義とされて家に帰ったのは、このファリサイ派の人ではなく、遠くに立って、目を天に上げようともせず、自分の罪を悔いながら祈っていた人、すなわち、徴税人だったのです。
主イエスは、乳飲み子も幼子も、そして子供たちも、一人ひとりを同じように、深く愛しておられます。
そして、主イエスの方から、子供たちに近寄って来てくださる方です。そして主イエスは「子供たちをわたしのところに来させなさい、妨げてはならない。」と言われました。このとき主イエスは強い口調で言われたどうかは分かりませんが。心の中には強い思いがあったことでしょう。
本日箇所について、その要点を整理いたします。
第一のポイントは、主イエスは子供たちをこよなく愛しておられる、ということです。ここでの「子供」という言葉には年齢の制限はありません。すべての子供たちを愛しておられた、ということです。
このことを本日箇所に登場する弟子たちは、残念ながら理解していたとは思われません。主イエスの方にだけ目が、そして心も向いていた、としか考えられません。
第二のポイントは、その子供たちを主イエスは招いていてくださる、ということです。主イエスは「子供たちをわたしのところに来させなさい。妨げてはならない。」と招いておられたのです。
志村教会にはかつて幼稚園があり、沢山の子供たちも来ていました。そこで働いておられた方も沢山います。そのことを思い出しておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。「こひつじえん」の教師たちは、園児一人ひとりに心から寄り添い、その保育に当たっておられたその優しい姿を今でも思い出します。
次へ進みます。16節の後半です。「神の国はこのような者たちのものである。」
これは文字道理の解釈で、“神の国は、年齢的に幼い者たちだけがいるところ”、という意味ではありません。年齢ではないのです。そうではなく、子供たちのような純真な心をもって神を信じる人たちを神は求めておられるのです。
かつて、小学校低学年の子供さんが信仰告白された時のことを思いだします。教会としてこの子供の信仰をどう扱っていったら良いかと、話し合いをもちました。今考えますと、大変うれしい出来事であり、信仰の原点を見た思いです。
16節b、17節を見ていきます。「神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。」とあります。
本日の説教題も、ここから採らせていただきました。
どうかわたしたちもこれから子供たちのように素直なそして清い心で、主イエスさまを、そして主なる神を信じ続けていきましょう。
そして主のために、わたしたちが用いられることを感謝して歩むことができますようにと、お祈りしていきましょう。