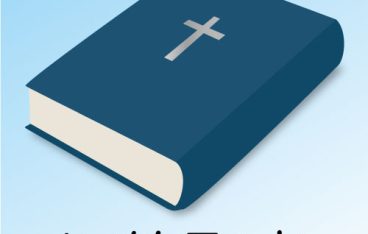2025年11月2日(主日)
主日礼拝『 主の晩餐 』
エレミヤ書 2章4~9節
牧師 常廣 澄子
エレミヤが生きて活動していたのは、今から2600年くらいも前のことですが、エレミヤに託された主の言葉は、今の私たちにも語られている言葉だと思います。エレミヤはイスラエル王国の最も大変な危機の時代に、主なる神ヤーウェの言葉を文字通り命がけで伝えたのです。
本日は2章の御言葉を読んでいきますが、2章から6章にかけて書かれていることは、エレミヤが預言者として活動を始めた初期の頃の預言であると言われています。ここにはいろいろな内容の事柄が時系列に関係なく縦横無尽に書かれています。
先ず2章2-3節には、神がイスラエルの民をご自身の選民としたことを思い出させることから始められています。イスラエルの民はもともとどういう状態であったのかということです。そして続く4-8節には、そのような状態であったイスラエルが、今やいかなる状態となってしまったかが語られています。それは、イスラエルがたどって来た過去の歴史を振り返り、現在を問題にすることによって、イスラエルの民に悔い改めを促しているのです。すなわち、神はイスラエルの民に、はじめの愛の関係に立ち帰って生きるようにと促しているのです。
エレミヤはまず2節で「主はこう言われる。わたしは、あなたの若いときの真心 花嫁のときの愛 種蒔かれぬ地、荒れ野での従順を思い起こす。」と語っています。「若いときの真心 花嫁のときの愛」という言葉でわかるように、神とイスラエルの民との関係は、結婚という例えを用いて語られています。
では、エレミヤは、神とイスラエルの民との関係をどうして親子の関係に例えずに、結婚という夫婦の関係に例えたのでしょうか。神とイスラエルの関係を婚姻関係になぞらえるのは、エレミヤの時代から100年くらい前に(紀元前8世紀)北イスラエルで活躍した預言者ホセアに顕著にみられるもので、親子の関係は血肉の関係であるが、夫婦の関係は約束の関係であるということです。すなわち結婚とは、相手を夫とし、あるいは妻として選び、生涯夫婦として助け合うことを約束して生きることです。神とイスラエルの民の場合には、主なる神がイスラエルの民を花嫁として選んだわけです。そのことを聖書では契約による関係というように言われています。イスラエルと神との関係は、このように約束を交わした関係であると同時に、互いの愛に支えられた血の通った人格関係としても捉えられています。
この関係を支え、切っても切れない命あるものとしているのが「若いときの真心 花嫁のときの愛」です。従って神とイスラエルの間にある関係は義務や束縛ではありません。人間と人間の場合を考えてみても、新婚の時にはお互いに義務や束縛など感じないのが普通ではないでしょうか。もちろん責任や義務がないわけではありませんが、真心と愛がありますから、互いの責任や義務を重荷に感じることはなく、互いに軽やかに幸せに過ごしています。エレミヤはここで、神とイスラエルの民の間にあったそのような状態を「はじめの愛」と語っています。
ここにある「愛」という言葉は、人間の自然な愛、本能ともいえるものであって、理屈を超えるものです。主なる神とイスラエルの民の間にある愛は、理屈ではないのです。神は無条件にイスラエルの民を愛し、イスラエルの民もまた無条件でその愛に応えています。また「真心」という言葉は、契約という枠の中にある愛のことです。先ほどの夫婦の関係でいうなら、夫として、また妻として、それぞれ責任ある立場に置いて愛する愛のことです。エレミヤはこの愛すべきイスラエルの民のことを「主にささげられたもの」「初穂」と呼んでいます。「2:3 イスラエルは主にささげられたもの 収穫の初穂であった。」
エレミヤは、出エジプト直後の、神とイスラエルの民との関係をハネムーン時代として描いています。つまりイスラエルの民がモーセによってエジプトから導き出され、シナイの荒れ野を旅していた時代は、主なる神とイスラエルの民の間には「若いときの真心 花嫁のときの愛」がありました。すなわち民にとっては、この神の他には神として存在する何者も知りませんでしたし、神もまたイスラエルの民以外のいかなる民をもご自分の民とはされなかったのです。両者の間には何者も入り込んでいませんでした。神は何ら功なき貧弱な民族であるイスラエルの民に心惹かれて「宝の民」とし(申命記7章6-7節参照)、他方イスラエルは、「心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、神を愛し慕う」(申命記6章5節参照)「真心」に満ちていたのです。
ところが、そのように親しく仲睦まじく神との関係を保っていたイスラエルの民でしたが、自分たちをエジプトでの奴隷生活から解放してくださり、死の陰の谷や人の住まない荒れ野をも生き延びさせてくださった神を忘れるのに時間はかからなかったのです。契約は破られ、互いを重んじ合う関係は終わりを告げてしまいました。イスラエルの民の一方的な契約破棄という事態です。神はそのような不条理を驚き怪しみ、一体どうしてなのか、と問うておられるのがこの個所です。
戸惑いを隠さずに、「2:4 ヤコブの家よ イスラエルの家のすべての部族よ 主の言葉を聞け。2:5 主はこう言われる。お前たちの先祖は わたしにどんなおちどがあったので 遠く離れて行ったのか。彼らは空しいものの後を追い 空しいものとなってしまった。2:6 彼らは尋ねもしなかった。『主はどこにおられるのか わたしたちをエジプトの地から上らせ あの荒野、荒涼とした、穴だらけの地 乾ききった、暗黒の地 だれひとりそこを通らず 人の住まない地に導かれた方は』と。」と嘆いています。
この後の21節でも「2:21 わたしはあなたを、甘いぶどうを実らせる 確かな種として植えたのに どうして、わたしに背いて 悪い野ぶどうに変わり果てたのか。」23節でも「2:23 どうして、お前は言い張るのか わたしは汚れていない バアルの後を追ったことはない、と。見よ、谷でのお前のふるまいを 思ってみよ、何をしたのか。お前は、素早い雌のらくだのように 道をさまよい歩く。」29節でも「2:29 なぜ、わたしと争い わたしに背き続けるのか、と主は言われる。」等々、イスラエルの民に対して、「どうして…なのか?」「どうして…なのか?」と何度も何度もその不可解な行動を問うておられます。
イスラエルの民はモーセに導かれて奴隷の国エジプトから救い出されました。そればかりか、モーセは彼らを導いて「2:7 わたしは、お前たちを実り豊かな地に導き 味の良い果物を食べさせた。」と言われています。いわゆる乳と蜜の流れるカナンの地に導き入れられたのです。ところが、彼らはこのような神の特別の計らいや恵みの計画に正しく答えたでしょうか。彼らは神への恩を仇で返したのです。「2:7後半 ところが、お前たちはわたしの土地に入ると そこを汚し わたしが与えた土地を忌まわしいものに変えた。」神が与えられたカナンの地の美しい自然は、民がその地の異教の神を礼拝することによって汚されてしまいました。
何が彼らをそのようにさせたのでしょうか。それは彼らが神の恵み、その愛と真心を忘れてしまったからです。ここにはイスラエルの民が、真の神(ヤーウェの神)を捨ててカナンの土着の神であるバアルに従ったという、神の愛への裏切り行為がはっきり示されています。5節にあるように、「彼らは空しいものの後を追い 空しいものとなってしまった。」のです。
この後の11~13節では、空しいものの後を追うイスラエルの民のことを、このように語っています。「2:11 一体、どこの国が 神々を取り替えたことがあろうか しかも、神でないものと。ところが、わが民はおのが栄光を 助けにならぬものと取り替えた。2:12 天よ、驚け、このことを 大いに、震えおののけ、と主は言われる。2:13 まことに、わが民は二つの悪を行った。生ける水の源であるわたしを捨てて 無用の水溜めを掘った。水をためることのできない こわれた水溜めを。」
エレミヤは民に向かって、古代のいかなる民族が先祖の神を取り替えたことがあろうかと嘆いています。少なくともより役に立たない偶像物と取り替えるなどとは、何と情けないことかと語っています。そして神との契約関係にあるイスラエルの民は、二つの重要な過ちを犯したのだと言うのです。それはすなわち生ける真の神を捨てたことと、偶像の神に仕えることを選んだことです。ここでは真の神を「生ける水の源」、つまり永遠の命の水を湧き出させる泉と表現し、人間の手で造られた価値のない偶像を、命を保持するのには何の役にも立たない水漏れする「こわれた水溜め」に例えています。結局、この後、イスラエルの民は、私たち人間の深い霊的必要を満たすことができなくなってしまったのです。
イスラエルの民は、荒野を旅していた時には、主なる神ヤーウェが自分たちを導く神であることを知っていました。しかし、カナンに到着してしばらく経つうちに、それを忘れてしまったのです。人間がいかに形あるもの、きらびやかなもの、人目をひくものに引き寄せられやすいかがわかります。本来、神との契約関係にあるイスラエルの民は、たとえ異教の神を拝むカナンにあったとしても、目に見えない神を信じて従って行くことがいかに頼りなく見えたとしても、カナン人のように生きてはならず、なお契約の民であるイスラエルの民としてあり続けなくてはならなかったのです。しかしこれはなかなか簡単ではありませんでした。しかし簡単ではないかもしれないけれども、神は「はじめの愛」を彼らに求めていたのです。バアルを信じるカナンの地にあったとしても、イスラエルの民は主なる神ヤーウェの名を呼ぶべきでした。
エレミヤは6節で「2:6 彼らは尋ねもしなかった。『主はどこにおられるのか わたしたちをエジプトの地から上らせ あの荒野、荒涼とした、穴だらけの地 乾ききった、暗黒の地 だれひとりそこを通らず 人の住まない地に導かれた方は』と。」と嘆いています。神をたずね求め、御声に聞き従おうとする生き方こそ、イスラエルが取るべき態度でした。
また8節では「2:8 祭司たちも尋ねなかった。『主はどこにおられるのか』と。律法を教える人たちはわたしを理解せず 指導者たちはわたしに背き 預言者たちはバアルによって預言し 助けにならぬものの後を追った。」というように、ここには「祭司たち」「律法を教える人たち」「指導者たち」「預言者たち」という四つの指導者階級がいたことがわかりますが、彼らのように律法を教える指導者たちでさえも、主なる神を理解していなかったのです。もし彼らが真の神に対する信仰に立って人々に教えていたら、このような霊的危機は起こらなかったかもしれません。彼らはカナンの人たちの宗教生活に影響されて、だらしなくも無責任な働きしかできなかったのです。つまりイスラエルの民が「私たちの主はどこにおられるのか」という問いを忘れた時、彼らは神の民として正しい信仰生活をすることができなくなってしまうということです。社会の精神的、政治的指導者たちの堕落こそが人々を破滅に導くものであるとエレミヤは預言しているのです。
日本には今なお異教の神々がたくさん存在しています。教会から一歩外に出るならば、そこは異教の神々が支配する世界であり、日本の教会の多くはそういう環境に置かれています。確かに私たちはそういう社会に生かされていますが、少なくとも私たちは主を信じるキリスト者として、その信仰の姿勢や立場を守って行かなくてはなりません。しかし、それはただ、外見上のキリスト者らしい生活とか形の問題というだけではありません。そのもっと奥にある心、霊、精神の問題です。キリストを信じる信仰生活とは、どのような時代に生きていようと、どのような場所に置かれていようと、「主なる神は今どこにおられるのか」という問いを生涯問い続けることに他なりません。つまり神をたずね求め、御声に聞き従おうとする生き方です。場所が変わっても、時代が変わっても、この問いを根気強く続けることによって、「はじめの愛」から転落したり、逸脱してしまうことから免れることが出来るのではないでしょうか。エレミヤ書の言葉はそれを教えてくれているのだと思います。