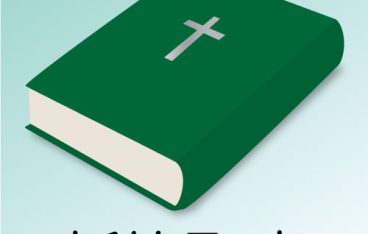2025年4月13日(主日)
主日礼拝『 誕生日祝福 』
ルカによる福音書 17章11~19節
牧師 永田 邦夫
いま、わたしたちは受難節(レント)を過ごしております。そして来る4月20日には、イースター礼拝(召天者を覚えて)があり、さらにその先の4月26日(土曜日)には墓前礼拝を予定しております。
今週は受難週です。わたしたちは主イエス・キリストの受難と復活を覚えながら過ごしていくことが出来ますようにと願っています。
ところで、ルカによる福音書には、主イエスがご自身の十字架の受難と復活を予告されたことが記されておりまして、それは9章21~27節、18章31~34節です。
この中から、9章22節の言葉を紹介しますと、「人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日目に復活することになっている。」とあります。この記述の中で特に印象的な部分は、最後の部分の、「三日目に復活することになっている。」です。
主イエスは、十字架の受難とその死から三日目の復活は、父なる神が自分に定めてくださったことで、自分が果たさなければならない役割(務め)であることを強く自覚されていたのです。わたしたちもこのことはよく理解することができます。
主なる神はその御子イエスをこの世に送り、イエスの三年間の公生涯を通して、わたしたちに種々のことを教えてくださり、最後にわたしたちの全ての人の身代わりとなって罪の赦しのために、十字架にかかって死んでくださったのです。その身代わりの死をもって、わたしたちを生かし、新しい命をわたしたちに与えてくださったのです。
以上のことが、主イエスの受難と十字架の予告の中にすでに含まれているのです。
では本日箇所に入っていきます。その冒頭には「重い皮膚病を患っている十人の人をいやす」とかなり詳しい小見出しがついています。
11節には「イエスはエルサレムへ上る途中、サマリアとガリラヤの間を通られた。」とあります。この表記について聖書学者には、正確に表記されていない、などの諸意見があるようです。
しかしわたしたちは、聖書地図などを参考に、主イエスが故郷のガリラヤから、それに続くサマリアを通って、エルサレムを目指し進まれており、その途中で、ある村まで来たときの出来事であることが分かります。
12節、13節を見ていきましょう。「ある村に入ると、重い皮膚病を患っている十人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったまま、声を張り上げて、『イエスさま、先生、どうか、わたしたちを憐れんでください』と言った。」とあります。これ等の言葉から、当時この重い皮膚病を患っている人たちは、まとまって集団を形成し、一般の健康な人々が住む場所から距離を取って生活していたことをうかがい知ることができます。
では、主イエスが来られる前の旧約聖書の時代には、この重い皮膚病を生活の中でどのように認識し、共に生きていたか、その様子をレビ記の13章、14章から確認していきましょう。
レビ記13章の1節、2節には「主はモーセとアロンに仰せになった。もし、皮膚に湿疹、斑点、疱疹が生じて、皮膚病の疑いがある場合、その人を祭司アロンのところか彼の家系の祭司の一人のところに連れて行く。」とあります。
そして3節には「祭司はその人の皮膚の患部を調べる。患部の毛が白くなっており、症状が皮下組織に深く及んでいるならば、それは重い皮膚病である。祭司は、調べた後その人に『あなたは汚れている』と言い渡す。」とあります。
このように、その患者を担当する祭司は、途中の症状観察などを詳しく行っていたことが記されています。
当時の、祭司の役割は、現代で言いますと、ある部門での専門医のような役割を果たしていたと考えることができます。
以上のごとく、このレビ記の13章には、皮膚病に関することが、13章全体59節を費やして記されています。また続く14章には、重い皮膚病を患っていた人が癒されたときの「清めの儀式」について、これもまた極めて詳しく記されています。
このように、重い皮膚病は当時の人々の生活にとっては、身近で極めて重要な事項であったことを知ることができます。
日本における、キリスト教関係での「救らい活動」(当時はこの言葉を使っていたので、ここでも用いさせていただく)は、16世紀のキリシタンに遡ります。1557年、宣教師のアルメイダが豊後府内に病院を建てたのを皮切りとして、堺、京都、大阪、長崎、江戸などに宣教師や信徒らが小さな「らい院」を建てました。しかし1630年代までに、多くの施設は、キリシタン迫害、弾圧によって大打撃を受け、建物の破壊や患者の追放が起こった、と言います。
ここには、非常に残念な歴史も含まれています。
近代日本の救らい活動は、仏、米、英、から来日した宣教師らによって着手されました。その後時代が下り1996年の予防法廃止を機に、キリスト教界でも、過去の歴史について謝罪を公にしております。
また、ハンセン病者の希望を受け入れて、新共同訳聖書では「らい病」から「重い皮膚病」への表記変更となっている、とのことです。(以上は、岩波版キリスト教辞典の1170ページ記載から)
では、聖書の本日箇所に戻り、さらに詳しく見て参りましょう。
12節で、重い皮膚病を患っている十人が出迎えてくれたのですが、なぜ十人なのかは分かりません。また、そのことが問題でもありません。
わたしたち志村バプテスト教会はそれぞれが振り返ってみましても、それぞれに種々な思い出が詰まっております。会堂が火災で焼失したとき、その悲しみと落胆を共有しつつ、早速その再建に取り組んで参りました。そしてその再建が実現して、共に新しい会堂での礼拝を迎えたときの感激は、今でも忘れることができません。
一方、蓮根教会への株分けのときは、わたしたちそれぞれに悲喜交々の気持ちがあり、一つの教会を産み出した喜びもあり、教会員が分かれることの悲しみもありました。このことの中には、種々思わされることも残っております。
長くなりましたが、聖書の本日箇所に戻りましょう。
12節、13節「ある村に入ると、重い皮膚病を患っている十人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったまま、声を張り上げて『イエスさま、先生、どうか、わたしたちを憐れんでください』と言った。」とあり、これは共に課題を抱えながらも、今は心を合わせて、主イエスに対して癒しを願っている姿がここにあります。
その時の彼らの心は、ガリラヤ人、サマリア人などの隔ての壁は全く無く、心を一つにして、主イエスに、自分たちの抱えている重い皮膚病の癒しを願い、主イエスに憐みを訴えているのです。
これは本当に素晴らしい姿だと思わされます。
既にふれてきましたが、わたしたちは、普段は皆一つになって、声を大にして、人に何かを訴えることはあまりありません。特に都会生活では、隣近所と一体となって何かをするということは殆どありません。私など、田舎から都会に移り住んできた時には、特にそのことを感じさせられた経験があります。
聖書に戻り、重い皮膚病の人たち十人の訴えを聞いた主イエスのお言葉が次の14節にあります。
「イエスは重い皮膚病を患っている人たちを見て『祭司たちのところに行って、体を見せなさい』と言われた。」とあります。このとき主イエスは、ご自分でその患者の人たちを見たり、触ったりして癒しのわざをするのではなく、旧約聖書の時代から、このことを専門的に見て来た祭司のところに行くように、そして祭司に自分の体を見せるように、と指示しております。“餅は餅屋”との諺があるようにです。
このときの主イエスは、決して“あなた任せ”で、祭司のところに行きなさい、とだけ命じたのではなく、その重い皮膚病の患者たちのことを遠くで祈っておられた、とわたしは思います。
14節の後半には「彼らは、そこへ行く途中で清くされた。」とあります。この記述の背景には、前述の通り、主イエスの祈りがあってのことと信じています。
15節には「その中の一人は、自分がいやされたのを知って、大声で神を賛美しながら戻って来た」とあります。本当に拍手喝采であり、本当に嬉しい出来事です。
続く16節には「そして、イエスの足もとにひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった」とあり、感謝を告げるために戻ってきた人の出自まで記されています。
すなわち、主イエスのお言葉によって、祭司のところに行って、体を癒され、清くされたのは、始めから登場している十人でしたが、感謝のために、神を賛美しながら主イエスのもとに戻って来たのは、たったの一人だったのです。しかしそれは、「サマリア人だった」ことがわざわざ記されています。
ここには大きな意味があります。人は日常的に多くのことを経験します。嬉しいことや良いことも沢山あり、また残念ながら、悪いことも嫌なことも沢山あります。ここで、わたしたちが考えなければいけないことは、その一つひとつに主なる神が働いておられます。また、家族や多くの人の関りもあります。
わたしたちは人に感謝を表す時、その全体に対してではなく、その一つひとつに感謝することが大事です。わたしたちは、感謝をすることがいかに少ないか、そして疎いかを感じさせられています。
そして、聖書にもう一つ記されていたことは、「この人はサマリア人だった」ということです。このサマリア人は当時ユダヤの人々との確執があり、その両者の間柄はよくありませんでした。
本日の聖書個所も然りです。主イエスのお言葉によって重い皮膚病がいやされた十人は、恐らくユダヤ人が多くいたかもしれません。しかし今、主イエスにお礼の言葉を告げにもどって来たのは、サマリア人、たった一人だったのです。このことに関してわたしたちは非常に心の痛みを感じざるを得ません。
次は最後の19節の言葉「それから、イエスはその人に言われた。『立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。』」とあります。重い皮膚病だった人は、主イエスさまのこのお言葉によって大きな力を戴き、その後の生活へと立ち進んでいったことでしょう。
わたしたちも日頃、主なる神、主イエスさまからいただいている多くの恵みとお力に感謝しながら、これからも力強く生かされて参りましょう。