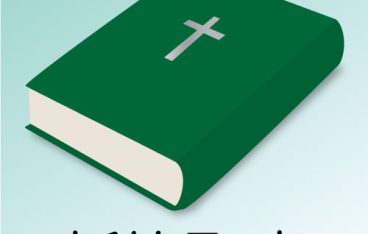2025年7月20日(主日)
主日礼拝
ルカによる福音書 18章1~14節
牧師 永田 邦夫
本日も皆さんと共に、ルカによる福音書からのメッセージをお聞き出来ますことを、主なる神に感謝いたします。
新共同訳聖書の本日箇所には、「やもめと裁判官」のたとえ、との小見出しがついています通り、主イエスがたとえを用いて弟子たちを教え諭している箇所です。
“たとえを用いて弟子たちに教え、また伝える”、これは主イエスが普段、日常的に用いられている教えであり、大切な方法でもあります。
そしてその教えの内容は、祈りについての教えです。祈りは、わたくしたちクリスチャンに取って、また神によって造られ、生かされている全ての人間にとっても大切なことです。そのことも先ず確認させていただいてから、本日箇所に入っていきましょう。
少々長くなりますが、本日箇所に入る直前の数章を確認しておきましょう。
主イエスはご自身の十字架の死と復活を二度にわたって予告してこられました。
その第一回目は9章21節~27節、第二回目は同じく9章43節b~45節です。そして、現実にその時期が迫って来まして、今はエルサレムに向かっての旅の途上にあります。そのことが9章51節から56節に記されています。
なお、旅の途上での主イエスの教えの中で、よく知られていて、わたくしたちにも馴染みの深い教えが、本書15章の「見失った羊」のたとえ、「無くした銀貨」のたとえ、そして、「放蕩息子」のたとえ、等々です。
では早速本日箇所18章に入っていきます。
1節で、主イエスは「気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために、弟子たちにたとえを話された。」として、そのたとえが2節から5節に記されております。
そして登場人物は、裁判官とやもめです。しかし新共同訳聖書ではなんの躊躇もなく、寡婦のことを“やもめ”と言っているのが気がかりで許せません。
裁判官の紹介が2節にあり「ある町に、神を畏れず人を人とも思わない裁判官がいた。」との紹介です。
考えてみますと、裁判官とは、現実の社会のなかで弱くされ、辛さや悲しみを抱えながら生きている人に寄り添いながら、その問題点や課題をよく聞いたうえで、その問題点を改善してあげたり、取り除いてあげる、これが裁判官に求められている姿であり、また、求められている仕事です。
ところが、すでに2節で読みましたように、本日箇所に出て来る裁判官は、その期待やあるべき姿とは真逆で、「神を畏れず、人を人とも思わない」人です。これはとんでもない裁判官であり、また許せない裁判官です。この聖書箇所を読む度に辛い思いにさせられます。
次は3節に入ります。「ところが、その町に一人のやもめ(寡婦)がいて、裁判官のところに来ては、『相手を裁いて、わたしを守ってください』と言っていた。」とあります。この3節から読み取れますことは、この寡婦が、先ほどから登場している、悪裁判官のところに行っては、何とかしてほしいと頼み込んでいる。それも一回や二回に留まらず“度々のことだった”と読み取れます。
そして次の4節aには「裁判官は、しばらくの間は取り合おうとしなかった。」とあります。ここまでは、依然としてどうしようもない裁判官の姿が記されています。
ところが次の記述、4節b及び5節を見ますと事態は一変していきます。
「しかし、その後(のち)に考えた。『自分は神など畏れないし、人を人とも思わない。しかし、あのやもめは、うるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう。さもないと、ひっきりなしにやって来て、わたしをさんざんな目に遭わすに違いない。』」と、その変わり方の一片が記されています。
今までは、取り合おうとしなかった裁判官が、彼女のために裁判をしてやろう、という気になったのです。
しかし、この変化の記述を見ますと、確かに変わって来てはいますが、その要因はちっとも変わっていません。依然として自分中心に考え、自分に都合がいいように行動を決めているのです。言ってみれば「自分勝手であって、他人のことをちっとも考えていない自分勝手な裁判官」です。
何度も言いますが、裁判官とは、「世の中の弱者や、困っている人と向き合いつつ、その問題点、課題を考え、その痛み・弱みをとり除いていあげる」これが裁判官に求められる役割なのです。
この現象は、現代の社会でも見られます。特に政治の世界や、経済界の上の方によく見られる現象です。本来、政治とは、世の中の問題点を改善し、住みよい社会に変えていくこと、これが政治の役割であり、期待される姿です。
ここで今まで述べて来たたとえは終了し、ここからは著者ルカの考えであり、また、わたくしたちの考えや願いを代弁しているようにとれます。
6節、7節には「それから、主は言われた。『この不正な裁判官の言いぐさを聞きなさい。まして神は、昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでもほうっておかれることがあろうか。』」とあります。
そして8節aには「言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。」とあります。
その神に注目いたしましょう。
神は、この世で弱くされている人、苦しんでいる人をいつまでも放っておかれません。その人につき添いながら、速やかにその苦しみや弱さを取り除いてくださる神です。その神をわたくしたちは信頼しながら、その神と共に生きて生きたいと思います。このことを、本日箇所の今までのところから思わされています。
この願いを持ちながら次の8節bに移りますと、「しかし、人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見いだすだろうか。」と結んでいます。この世の人々は、神の思いを理解し、そしてその神の思いに少しでも近づこうとして努力を重ねていくのではなく、神の思いを無視したり、また神の思いと逆の方向に走ってしまう、そのような心配が先に立ってしまう世の中です。
ここで、ヨハネの黙示録21章3節、4節を見てみましょう。
「そのとき、わたしは玉座から語りかける大きな声を聞いた。『見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとくぬぐい取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも労苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。』」
以上は本当に感動的な聖句です。このような世界になりますようにと願いつつ、わたくしたちキリスト者も日々励んでいきましょう。
では、二つ目の段落に入ります。ここには「ファリサイ派の人と徴税人」のたとえ、との小見出しがついている通り、この二種類の人が登場します。
そして、「ファリサイ派の人」は、主イエスの教えや例話の箇所に登場してきますが、その教えの中では、中心人物というよりも脇役として登場することが多いように感じます。
また「徴税人」もほぼ同様です。この徴税人について、少し触れますと、この徴税人は、文字通り、税の徴収権を、時の支配者であるローマから委嘱されて税を取り立てる仕事をしていたのですが、個々の徴税額については、その徴税人に任されていたのです。そこが問題点ですが、ここではそれ以上触れないことにします。
次の10節以下に入っていきます。「二人の人が祈るために神殿に上った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。」ここまでは、いわばイントロです。
神殿で祈っているとき、何があったのか、11節以下にありますので見ていきます。
11節「ファリサイ派の人は立って、心の中でこのように祈った。」とあり、12節にその祈りの内容が記されています。早速見ていきましょう。
12節「神様、わたしはほかの人たちのように、奪い取る者、不正な者、姦通を犯す者でなく、また、この徴税人のような者でもないことを感謝します。わたしは週に二度断食し、全収入の十分の一を献げています。」との祈りです。ところで、この祈りの内容は、当時彼らが自負していて、外に向かってアピールしていた内容そのままです。
この祈りを、皆さまどのように受け止め、そして判断しますでしょうか。
ここでも、これ以上触れません。
次は、徴税人の祈りを見ていきましょう。13節です。「ところが、徴税人は遠くに立って、目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。『神様、罪人のわたしを憐れんでください。』」と、全く姿勢も心も低くしての祈りです。わたくしはこの箇所を読んだ時、本当に胸にジーンときました。しばらくは言葉が出てきませんでした。
神の前に謙遜、そして姿勢を低くして祈る、とはこのことだな、と思わされました。
14節「言っておくが、義とされて家に帰ったのは、この人であって、あのファリサイ派の人ではない。だれでも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。」
このお言葉を胸に刻みながら、わたくしたちは、これからもキリスト者として、主に励まされながら、力強く日々を生きてゆきましょう。