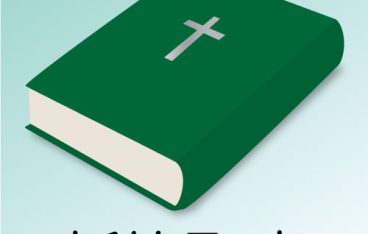2025年7月27日(主日)
主日礼拝
使徒言行録 13章1~12節
牧師 常廣 澄子
お読みしているこの使徒言行録は、内容的にここで大きく二つに分かれています。今まで読んできた1章から12章までと、本日からお読みする13章から最後までです。前半では宣教活動の中心はエルサレムでしたが、ここから宣教活動の基点はアンティオキアに移っていきます。また、宣教の主役がペトロからパウロに替わっていきます。そして、宣教の対象もユダヤ人から異邦人(ユダヤ人以外の民)に移っていくのです。このようにしてすべての人に対する神の救いの計画が着々と進められ、主の福音の本質が明らかになっていくのです。主なる神を信じるキリスト教はユダヤ人という一つの民族だけのものではありません。この救いの神はすべての民族、すべての国民の神であることを伝えていくことが、この使徒言行録の目的でもあるのです。
アンティオキアに歴史上はじめて異邦人教会ができたいきさつは、以前にお話しましたが(11章19-30節参照)、これからはここが拠点となって、世界に向かっての宣教活動がスタートしていくのです。これまでは(ステファノが殉教した時の様子を思い出してみてもおわかりのように)迫害を逃れるために各地に散って行ったクリスチャンたちを通して福音が伝えられていきました。しかし、このアンティオキア教会は、「まだ主の福音を聞いたこともない人たちに対して、キリストの救いの福音を伝える」というはっきりした目的をもって宣教師を送り出したのです。その歴史的宣教活動の最初の伝道地がキプロス島でした。
アンティオキア教会は、できてからまだ日の浅い若い教会ですが、11章に書かれていたように、エルサレム教会から派遣されたバルナバと、バルナバがタルソスまで行って捜して連れてきたサウロ(パウロ)、この二人が丸一年間指導したことによって(11章26節参照)、アンティオキア教会は急速に成長して、預言する者や教師として立派な指導者たちが次々と起こされていました。1節にその名前があげられています。「13:1 アンティオキアでは、そこの教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナエン、サウロなど、預言する者や教師たちがいた。」
「ニゲルと呼ばれるシメオン」は、たぶんアフリカ出身の黒人ではないかと推測されます。もしかしたら、イエスの受難の際に、無理やり十字架を背負わされたあの「キレネ人シモン」(マルコによる福音書15章21節)であったかもしれません。(キレネもしくはクレネは、北アフリカにあるギリシアの植民都市の名前です。)次に書かれている「キレネ人ルキオ」はおそらく前の11章20節に書かれていたキレネ人の一人ではないかと思われます。その次の「領主ヘロデと一緒に育ったマナエン」このマナエンは、ヘロデ大王の息子ヘロデ・アンティパスと乳兄弟と言われています。王子と一緒に宮廷で育てられたのだとしたら、身分の高い家柄の出であったのでしょう。この三人に加えて、キプロス島出身のバルナバと小アジアのキリキアのタルソス出身のサウロが、このアンティオキア教会の主な指導者でした。実にいろいろな民族が加わっていて、当時のアンティオキア教会の多様性がわかります。異なる習慣や文化を持った人たちからなるアンティオキア教会は、人種や社会的地位を超えて、信仰によって一致していたことがよくわかります。
さて、このアンティオキア教会から世界宣教が始まっていくきっかけは、大変興味深いものです。それは人間が考えて計画したものではないのです。あるいは教会で何度も協議を重ねて検討されたものでもありません。その宣教命令は聖霊が告げたのです。「13:2 彼らが主を礼拝し、断食していると、聖霊が告げた。『さあ、バルナバとサウロをわたしのために選び出しなさい。わたしが前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。』」
復活のイエスが語られた大宣教命令と言われるお言葉がありますが(マタイによる福音書28章18-20節)、「28:18 イエスは、近寄って来て言われた。『わたしは天と地の一切の権能を授かっている。28:19 だから、あなたがたは行って、すべての民をわたしの弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、28:20 あなたがたに命じておいたことをすべて守るように教えなさい。わたしは世の終わりまで、いつもあなたがたと共にいる。』」復活のイエスが、このお言葉を語られた時も、弟子たちは主を礼拝していました。世界宣教という働きは、常に主を礼拝している教会の民に委ねられるのです。
罪赦された者たちが、感謝の心で集まってきて主なる神を礼拝する時、主なる神はその真ん中にいてご自身の愛と救いの計画を示さずにはおれません。アンティオキア教会でも、主なる神は聖霊を通してそのことを告知されました。たぶんここで「預言する者」と言われている人たちがそれを取り次いだのだと思います。「13:3 そこで、彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。」そこで教会はただちに断食と祈りで神のみ旨を確認してから、バルナバとサウロを公認の宣教師として派遣することにしたのです。礼拝も断食も祈りも、私たちが神に全身全霊を明け渡すという行為です。そしてここに「二人の上に手を置いて」とありますが、この按手は教会と派遣される宣教師たちがつながりあう共同の関係にあることを示しています。宣教の働きは、宣教師だけの働きではありません。彼らを送り出し支えていくこと、これは神の業を担う教会の働きなのです。
「13:4 聖霊によって送り出されたバルナバとサウロは、セレウキアに下り、そこからキプロス島に向け船出し、13:5 サラミスに着くと、ユダヤ人の諸会堂で神の言葉を告げ知らせた。二人は、ヨハネを助手として連れていた。」アンティオキアから地中海に面するセレウキアに行き、そこから船出するのですが、このようにして始まった福音宣教の旅は、パウロの第一回伝道旅行と言われています。そしてこの旅行を導いているのは聖霊ご自身であることが4節にはっきり書かれています。実際この働きは人間が考えたものではありませんでした。
このキプロス島はバルナバの出身地でした(4章36-37節)。アンティオキア教会にもキプロス島生まれの信徒がかなりいたでしょうから、バルナバにとってはずっと心に懸け祈っていた郷里伝道ができる喜びがありました。そしてこの伝道旅行にはヨハネ・マルコが助手として同行していました。彼はバルナバのいとこです(コロサイの信徒への手紙4章10節参照)。また彼は後にペトロの筆記者になったと言われていますから、この旅行でもバルナバとサウロの説教を記録する役目を持っていたのかもしれません。
一行は船でキプロス島の東海岸にあるサラミスに着くと、ユダヤ人の諸会堂で神の言葉を告げ知らせました。パウロの伝道の旅では、先ず最初に、決まってユダヤ人の会堂を足場にして伝道を始めています。それはやはりユダヤ人と神とが特別な契約の民であることを意識していたからではないでしょうか。その会堂を通して彼らは異邦人と出会い、語ることができたのです。
本日の週報に永田邦夫先生が書かれていますが、私たちの志村バプテスト教会では、以前は毎年のように、日本各地の教会や海外の教会にも伝道チームを派遣して、主の福音が一人でも多くの人に伝えられるようにと、福音伝道のために教会全体で祈り、捧げ、協力していた歴史があります。それは志村バプテスト教会が主に豊かに祝福されていた証しです。その時にはいろいろ事前に計画し、準備して行ったと思いますが、バルナバとサウロの伝道旅行は、下見も事前調査もありません。今とは事情が違いますが、その時その時に、聖霊の導きを祈り、敏感にその歩みを見極めながら進んで行ったのだと思います。
「13:6 島全体を巡ってパフォスまで行くと、ユダヤ人の魔術師で、バルイエスという一人の偽預言者に出会った。」サラミスから島全体を巡って、さらに進んで西海岸の方に出てパフォスに着くと、ユダヤ人の魔術師で、バルイエスという一人の偽預言者に出会いました。「13:7 この男は、地方総督セルギウス・パウルスという賢明な人物と交際していた。総督はバルナバとサウロを招いて、神の言葉を聞こうとした。13:8 魔術師エリマ――彼の名前は魔術師という意味である――は二人に対抗して、地方総督をこの信仰から遠ざけようとした。」ここで魔術師と言われているのは、当時、東方(特にペルシア地方)からやって来て、異教のまじないや奇術を行って人々を驚かせて、人々の信望を得て地位を確保していた人たちです。とりわけローマの高官は魔術師たちに興味をもっていたということが歴史書にも残っています。ここに書かれている魔術師エリマは、せっかく地方総督セルギウス・パウルスの信任を得ているのに、それが自分から今度はバルナバやサウロに移るのを恐れて邪魔をしたのだと思われます。
「13:9 パウロとも呼ばれていたサウロは、聖霊に満たされ、魔術師をにらみつけて、13:10 言った。『ああ、あらゆる偽りと欺きに満ちた者、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道をどうしてもゆがめようとするのか。13:11 今こそ、主の御手はお前の上に下る。お前は目が見えなくなって、時が来るまで日の光を見ないだろう。』するとたちまち、魔術師は目がかすんできて、すっかり見えなくなり、歩き回りながら、だれか手を引いてくれる人を探した。13:12 総督はこの出来事を見て、主の教えに非常に驚き、信仰に入った。」
9節からはパウロという名前が出てくるようになります。もともとサウロはユダヤ名であり、パウロはローマ名です。著者ルカは、これから先、ローマの統治下にある地域に伝道していくにはパウロがふさわしいと考えたのかもしれません。
パウロはこの魔術師と対決し、神の言葉に逆らって主の福音伝道を妨害するこの男に対して、厳しい態度で臨みました。聖霊に満たされ、魔術師をにらみつけて言ったのです。「お前は目が見えなくなって、時が来るまで日の光を見ることができないだろう。」するとたちまち魔術師の目がかすんできて、すっかり見えなくなってしまいました。パウロはこれを見て自分のダマスコ途上でのあの回心の出来事を思い起こしていたかもしれません。パウロは今まで見えていたものが見えなくなった時に、今まで見えていなかったものが見えるようになったのでした。魔術師エリマがその後どうなったのかは聖書に何も書かれていませんが、神の光によって主の救いに与っていて欲しいと思い.ます。
しかしエリマに起こった出来事を見た地方総督セルギウス・パウルスは、「13:12 総督はこの出来事を見て、主の教えに非常に驚き、信仰に入った。」魔術師の魔術をはるかに上回るほどの神の奇蹟を目の当たりにした総督は、実際大変驚いたに違いありません。しかし、総督はそのことによって信じたのではなく、主の教えに非常に驚いて信仰に入ったのです。それはパウロやバルナバが身を持って解き明かした言葉によるのです。
このように、キプロス島における世界宣教の初穂は、地方総督セルギウス・パウルスの回心でした。ローマの高級官僚がイエス・キリストを信じる信仰に入るということは、大変な勇気と決断を必要としたはずです。当時彼らに要求されていた皇帝礼拝をしない、あるいはローマの神々を拝まないということになれば、自分の地位も危ぶまれますし、時には命に危険が及ぶことも予測されたはずです。しかし、この地方総督は敢然として主への信仰を表明したのです。「聖霊に満たされて」伝道したパウロの言葉とその業には、神の力が溢れていたからでしょう。伝道は、キリストを信じる者がその人が心から、全身全霊で語ることによって、相手に伝わっていくのだと思います。私たちもそういう体験をしていきたいと願っております。