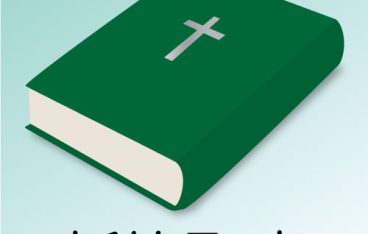2025年8月10日(主日)
主日礼拝『 平和礼拝・誕生日祝福 』
エフェソの信徒への手紙 2章11~22節
牧師 永田 邦夫
本日、わたしたち志村バプテスト教会は、主日礼拝を平和礼拝として奉げています。振り返りますと、今年に入って当初の頃はマスコミから「戦後80年」という言葉をよく聞きました。あの第二次世界大戦が終わってからもう80年経った、よって今は、平和な時代になっていますよ、との意味を込めての言葉だったかもしれません。
しかし、この平和について考えますと、いま現実にウクライナにおいて、また中東におい、戦争は止むことを知りません。本当に残念です。早くこれらすべての戦争が止んで、文字通り、今の世界が平和な世界へと変わって欲しい、そんな強い思いにさせられています。
本日の説教は、テキストとしてエフェソの信徒への手紙を選びました。本書は第二パウロ書簡(または「パウロの名による書簡」)とも言われまして、パウロが61年から63年頃にローマの獄中あったときの執筆によることから、獄中書簡とも言われます。
ところで、本書「エフェソの信徒への手紙」のテーマは、教会の栄光です。
教会の栄光とは、教会が現実のこの世にあって、率先して世界平和のために力を尽くしている教会の姿を表しています。すなわち、すべての人に期待されている通りの教会の姿を言います。
この手紙の宛先であるエフェソの教会は、パウロが第三回伝道旅行(53年から56年頃にかけて)のとき、エフェソに二年間滞在して伝道し、教会の基礎を作ったと言われています。
「パウロは会堂に入って、三か月間、神の国のことについて大胆に論じ、人々を説得しようとした。」(使徒言行録19章8節)、
パウロは、「テイラノという人の講堂で毎日論じていた。このようなことが二年も続いたので、アジア州に住む者は、ユダヤ人であれギリシア人であれ、だれもが主の言葉を聞くようになった。」(使徒言行録19章9節~10節)
以上のごとくパウロのエフェソにおいての伝道では多くの成果を結んだことが記されています。
本日箇所のエフェソの信徒への手紙2章に入りまして、11節からの段落に入る前の2章の1節から3節までを見ますと、次のように記されています。
「さて、あなたがたは、以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち、不従順な者たちの内に今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。わたしたちも皆、こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、ほかの人々と同じように、生まれながら神の怒りを受けるべき者でした。」とあります。
以上の御言葉には、執筆者のパウロが、イエス・キリストに入信する以前の生活の実態、心の実態をそのまま包み隠さず、赤裸々に告白しています。
ところが、次の4節から6節は、一転して、キリストを信じ、キリストを受け入れてからの歩み、祝福されたパウロの生活ぶりが次のように記されております。
「しかし、憐れみ豊かな神は、わたしたちをこの上なく愛してくださり、その愛によって、罪のために死んでいたわたしたちをキリストとともに生かし、――あなたがたが救われたのは恵みによるのです――キリスト・イエスによって共に復活させ、共に天の王座に着かせてくださいました。」とあります。
ではここで、永田が救い主イエス・キリストを信じて、キリスト者となったときのことを証しさせていただきます。
わたくしが29歳のときでした。当時、自分が落ち込んでいた様子を母(義母)が見ていて、「邦夫、近くに教会ができているから行ってみなさい」とわたくしに勧めてくれたのです。それが四月の初めの礼拝でした。今でも忘れることはありません。当日は、時田光彦牧師の説教の日でした。
そして説教は、出エジプト記からでした。イスラエルの民が長い間、エジプトで奴隷生活に苦しんでいた、そのような民に神が働きかけて、出エジプトを果たしていく、そのような内容の説教であったことを今でも覚えています。
当日の説教の内容が、わたくし永田の心を動かしてくださったと信じています。そして全てを主なる神が導いてキリスト者としてくださった、とわたくしは信じています。
では聖書に戻りまして、パウロがイエス・キリストを知らずに生きていた当時のこと、そしてイエス・キリストがパウロに働きかけ、パウロをキリスト者へと変えてくださったこと、そして最後は、共に天の王座に着かせられた、そのことをもう一度整理し確認しておきましょう。
第一段階:イエス・キリストへの入信前には、自分の犯した過ちと罪のために死んでいた。肉の欲望の赴くままに生活し、生まれながらの神の怒りを受けるべき者だった。(2章3節から)
第二段階:しかし、憐れみ豊かな神は、わたしたちをこの上なく愛してくださり、その愛によって、罪のために死んでいたわたしたちを、キリストと共に生かし、キリスト・イエスと共に復活させてくださった。
この段階では、憐れみ豊かな神は、一方的に、しかも自分が神を知る前から、わたしを愛してくださっていた、と記しています。(4節5節から)
第三段階:キリストと共に復活させてくださったわたしたちを、共に天の王座に着かせてくださった。(6節から)
以上のことが2章7節に次のように記されています。
「こうして、神は、キリスト・イエスにおいてわたしたちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを、来るべき世に現わそうとされたのです。」
このことを前提にして、本日の箇所である11節から22節に入ります。
11節には「だから、心に留めておきなさい。あなたがたは以前には肉によれば異邦人であり、いわゆる手による割礼を身に受けている人々からは、割礼のない者と呼ばれていました。」とあります。
端的に、ユダヤ人であるか、異邦人であるかを、割礼の有無と関連させて述べています。
次の12節ではユダヤ人とそして契約の律法と関連させ、「契約と関係ない者」と表現しています。
「また、そのころは、キリストとかかわりなく、イスラエルの民に属さず、約束を含む契約と関係なく、この世の中で希望を持たず、神を知らずに生きていました。」と、言葉の限りを尽くして自分の過去を言い表しています。
次の13節に入りますと、さらに要点をまとめて、次のように表しています。
「しかしあなたがたは、以前は遠く離れていたが、今や、キリスト・イエスにおいて、キリストの血によって近い者となったのです。」ここに書かれている「キリストの血によって」とは説明するまでもありません。キリストの十字架による贖いを信じる人はキリスト者とされていくことを表しています。
14節「実に、キリストはわたしたちの平和であります。」この言葉もちょっとわかりにくい言葉ですが、説明するまでもありません。
世界には、主義主張、政治理念など、思想や信条の異なる者同士が共に生き、そして活動し、集団を作り、国々を作っています。そのような人々が、それぞれの立場を受け入れながら世界秩序を保っていくのが、現代の国際社会ではないでしょうか。そのように相対立する者同士が、先ず相手を受け入れていかないと、社会は成立していきません。
このことは、わたしたちには十分理解できます。
14節a「実に、キリストはわたしたちの平和です。」この言葉は、対立する者同士が社会を形成していくときのコツを表している、とも理解できます。
14節b「二つのものを一つにし、御自分の肉において敵意とう隔ての壁を取り壊し、」とあります。この言葉は、主イエス・キリストが十字架の贖いにおいて、世界の平和の基礎をお造りくださった、と理解することです。
以上のことが次の15節bから16節にかけて記されています。
「こうしてキリストは、双方を御自分において一人の新しい人に造り上げて平和を実現し、十字架を通して、両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。」
主イエスは十字架上でご自分の体をも裂かれて、すべての人の罪を赦し、そして新しい命を、わたしたち信じる者すべてにお与えになったのです。なんという感謝なことでしょうか。