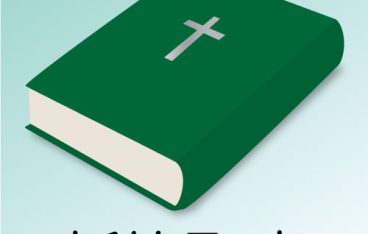2025年8月24日(主日)
主日礼拝
使徒言行録 13章13~43節
牧師 常廣 澄子
前回はバルナバの故郷キプロス島での伝道の様子を見てきました。キプロス島では、ローマ帝国から遣わされていた総督が主の福音を信じてクリスチャンになったのです。大きな成果です。彼らはその素晴らしい成果をもって、送り出されたアンティオキア教会に戻って行ったかと思いきや、彼らはそこから小アジアの方に向かって伝道活動を進めていきました。
そしてお気づきのように、今までは「バルナバとサウロ」という順序で書かれていた二人の名前が、この13節では「パウロとその一行」というように書かれていて、これ以降は「パウロとバルナバ」という順に変わっています。明らかにパウロの力が強まっていることが感じられ、大変興味深いことです。以前にお話ししましたが、回心したパウロがイエスの弟子の仲間に加わろうとしても、今までクリスチャンを迫害していた人物ですから、皆は不安や恐れなどの気持ちで危惧して仲間に入れないでいました。その時、バルナバはパウロを使徒たちの所に連れて行って、仲間入りが可能となるようにお世話したことがありましたし(9章27節参照)、身の危険を感じて故郷のタルソスに帰っていたサウロをわざわざ探し出し、アンティオキア教会に連れて来て教師の仲間に加えたのもバルナバでした。今まではバルナバあってのパウロだったのです。ところが、キプロス島の伝道を終え、パフォスから船に乗って小アジアに向かう時から、この順序が逆転して、パウロがリーダー格となっていったのです。
そしてこの時点で、バルナバの従兄弟であって一緒にキプロス島伝道に加わっていたヨハネ・マルコが、一行から身を引いてエルサレムに帰ってしまったのです。「13:13 パウロとその一行は、パフォスから船出してパンフィリア州のペルゲに来たが、ヨハネは一行と別れてエルサレムに帰ってしまった。」聖書にはその理由は何も記されていません。いくつか考えられることは、先ず若いマルコにとっては単なるホームシックがあったのかもしれません。また、このキプロス島伝道はバルナバの郷里伝道であったわけで、たぶんそのために同行したであろうマルコは、それが一応終わった段階でそれから先へはついて行く責任を感じなかったのかもしれませんし、これから先の伝道旅行の苦労を思うと気持ちがくじけてしまったのかもしれません。あるいはバルナバの従兄弟という立場のマルコにとっては、もしかしたらバルナバとパウロの間の力関係が逆転していったことへの不満があったのかもしれません。いずれにしても、マルコは戦列を離れました。バルナバの性格や人柄から想像すると、彼はきっと寂しい思いをしたでしょうし、心を痛めたことでしょう。しかしそれでもバルナバは気丈に旅を続けていったのです。
ヨハネ・マルコが欠けた一行は、海路パンフィリア州のペルゲに到着しました。ベルゲはパンフィリア州の首府でしたから伝道するには良い場所だったはずです。現在も残っている円形劇場や競技場などの遺跡の規模から推定すると、ベルゲは相当大きな都市だったようです。しかし彼らはその地に滞在することなく、さらに内陸地方に向かいます。タウロス山脈を上って海抜およそ千メートルの高原地帯にまで行きました。そこには「ピシディア州のアンティオキア」がありました。(このように言うのは、パウロたちを伝道に送り出したオロンテス河沿いにあるシリアのアンティオキアと区別するためです。)この町はローマ帝国領のガラテヤ州の中心地でした。(つまり「ピシディア州のアンティオキア」というのは、実際は「ピシディア州寄りにあるアンティオキア」と言った方が正しいのです。)一行はここに腰を据えて伝道活動をすることになります。パウロにとっては、ピシディア州の隣のキリキヤ州が自分の生まれ故郷ですから、いくらか親近感もあったことでしょう。この町には多くのユダヤ人がいました。パウロはいつも会堂を足掛かりにして伝道を開始しています。「13:14 パウロとバルナバはペルゲから進んで、ピシディア州のアンティオキアに到着した。そして、安息日に会堂に入って席に着いた。」先ずいつものように、安息日には会堂に入って席に着きました。
ユダヤ人たちが会堂で礼拝する時は、まずシェマーの祈り(イスラエルの民の信仰告白)から始めました。そして聖書朗読(律法と預言者の書の朗読)がありました。その後、今読まれた聖書箇所を説き明かす説教があるのです。この説教は、その地方のラビが担っていましたが、たまたまその会堂に来合わせたラビがいた場合には、その人が用いられる場合もあったようです。また、そこに参加していた人の中で、聖書を語るのにふさわしい人がいた時にはその人によってなされることもありました。イエスもそのようにして会堂で説教を求められたことがありました(ルカによる福音書4章16-22節参照)。これが現在、キリスト教会の礼拝の中で行われている説教の原型ともいえるものです。「13:15 律法と預言者の書が朗読された後、会堂長たちが人をよこして、『兄弟たち、何か会衆のために励ましのお言葉があれば、話してください』と言わせた。」ピシディア州のアンティオキアで、人々は会堂にパウロたちがいるのを見て、何か奨励して欲しいと頼んだのは自然なことでした。
「13:16 そこで、パウロは立ち上がり、手で人々を制して言った。『イスラエルの人たち、ならびに神を畏れる方々、聞いてください。』」会堂長から「何か励ましの言葉があれば話してください」と依頼されたパウロは、立ち上がって話を始めました。イエスもそうでしたが、会堂で教える教師は座って教えるのが普通でした。(ルカによる福音書4章20-21節参照)パウロが立ち上がって、手で人々を制したのは、人々を静めるためだったと思われます。
ここからパウロの説教が始まりますが、長さはステファノの演説の半分ほどですが、始めにイスラエルの歴史を語っているところなどはよく似ています。内容は大体三つに分類できると思います。最初は16-25節で、イスラエルの救いの歴史を簡単にたどっています。律法といわれる旧約聖書の始めの五巻に記されている歴史を手際よくまとめ、次にヨシュア記から列王記までの歴史を要約してダビデにつないでいます。つまりパウロはダビデに至るまでのイスラエルの歴史をまとめて語りながら、そこに貫かれている神の変わらない恵みの約束を示しているのです。それらの歴史の中で起きた出来事は、約束に基づいてキリストが出現するまでの準備期間でした。だから23節に「神は約束に従って、このダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださったのです。」とあります。その救い主がイエス・キリストであり、そのことを証言したのが洗礼者(バプテスマの)ヨハネです。パウロはヨハネの言葉を引用して最初の部分を締めくくっています。「見よ、世の罪を取り除く神の小羊だ」と言った洗礼者ヨハネの言葉はこのピシディアのアンティオキアでも離散のユダヤ人たちによく知れ渡っていたことがわかります。「13:24 ヨハネは、イエスがおいでになる前に、イスラエルの民全体に悔い改めの洗礼を宣べ伝えました。 13:25 その生涯を終えようとするとき、ヨハネはこう言いました。『わたしを何者だと思っているのか。わたしは、あなたたちが期待しているような者ではない。その方はわたしの後から来られるが、わたしはその足の履物をお脱がせする値打ちもない。』」
三つに分けた二つ目の部分は、26-37節です。この部分ではイエスの死と埋葬と復活を順に語りながら、イスラエルの民に拒否されたイエス・キリストこそが救い主であるということを証明しようとしています。せっかく神がイスラエルに救い主を送られたのに、人々も指導者たちもこのイエスを認めませんでした。「13:27 エルサレムに住む人々やその指導者たちは、イエスを認めず、また、安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めることによって、その言葉を実現させたのです。13:28 そして、死に当たる理由は何も見いだせなかったのに、イエスを死刑にするようにとピラトに求めました。13:29 こうして、イエスについて書かれていることがすべて実現した後、人々はイエスを木から降ろし、墓に葬りました。13:30 しかし、神はイエスを死者の中から復活させてくださったのです。」
パウロは、人々が十字架に架けて殺し、墓に葬ったその方を、神は死者の中からよみがえらせたのだ、と語ります。そしてそのことを目撃した証人が大勢いることも伝えます。「13:31 このイエスは、御自分と一緒にガリラヤからエルサレムに上った人々に、幾日にもわたって姿を現されました。その人たちは、今、民に対してイエスの証人となっています。13:32 わたしたちも、先祖に与えられた約束について、あなたがたに福音を告げ知らせています。」要するに、ここでパウロは、主の福音の要点を語っているのです。更にパウロはこれらすべてのことは、神が約束したことを果たしてくださったということなのだと、神の御言葉を次々と引用しながら説いているのです。
「13:33 つまり、神はイエスを復活させて、わたしたち子孫のためにその約束を果たしてくださったのです。それは詩編の第二編にも、『あなたはわたしの子、わたしは今日あなたを産んだ』と書いてあるとおりです。13:34 また、イエスを死者の中から復活させ、もはや朽ち果てることがないようになさったことについては、『わたしは、ダビデに約束した 聖なる、確かな祝福をあなたたちに与える』と言っておられます(この部分はイザヤ書55章3節から)。 13:35 ですから、ほかの個所にも、『あなたは、あなたの聖なる者を 朽ち果てるままにしてはおかれない』と言われています(この部分は詩編16編8-11節から)。」これらは神のイスラエルに対する約束が、イエスにおいて完成したことを示すものです。
最後の三つ目の部分は38-41節です。パウロはイエスを通して「罪の赦し」が成就したことを語ります。そしてパウロの話を聞いている人たちに決断を促しています。歴史的な事実を語るだけでは伝道とはいえません。福音はそれを聞いた人の心に決断を促すようでなければならないからです。すなわちパウロはイエスによる罪の赦しの福音を説いて聞かせ、「13:38 だから、兄弟たち、知っていただきたい。この方による罪の赦しが告げ知らされ、また、あなたがたがモーセの律法では義とされえなかったのに、13:39 信じる者は皆、この方によって義とされるのです。」と、私たちはただこのイエスを信じることによって義とされるのだと、福音の本質をはっきりと語っているのです。
パウロはかつてファリサイ派の厳格な信奉者であり、その時には、神に義と認められるためには、モーセの律法を事細かく細部に至るまで守らなくてはならないと理解していました。その点でかつてのパウロは誰よりも熱心だったのです。しかし、その努力にも限界があり、どんなに熱心であっても律法を完全に全うすることはできないこと、逆にいよいよ罪に敏感となり、罪の重さが増していくことがわかってきたのです。まじめであればあるほど、熱心であればあるほど、律法と現実とのギャップに悩む苦しみ、律法は喜びどころか、耐えられない重荷でしかなくなってしまいました。しかしそのパウロに復活のキリストが現れ、生ける神の御業を見て、初めて律法からの解放を味わったのです。そして「神に義と認められる」のは、律法を守る者ではなく、救い主イエスを信じる者であることがわかったのです。
最後にパウロは、この福音によって人々の悔い改めを促し、信仰を励ますために、旧約聖書のハバクク書1章5節の言葉を引用し、警告を持ってこの説教を閉じています。「13:41 『見よ、侮る者よ、驚け。滅び去れ。わたしは、お前たちの時代に一つの事を行う。人が詳しく説明しても、お前たちにはとうてい信じられない事を。』」これは、福音を信じる者は皆義とされ、罪の縄目から解放されるけれども、逆にそれほどにまで豊かな恵みの福音を無視し、拒否する者に対しては、裁きもまた厳しいのだということです。
さて、パウロの説教を聞いた人々の反応はどうだったでしょうか。人々は彼の説教を聞いて深く心を動かされ、次の安息日にも来て語ってくれるように願いました。求道心の現れです。「13:42 パウロとバルナバが会堂を出るとき、人々は次の安息日にも同じことを話してくれるようにと頼んだ。」また、大勢の人たちがパウロとバルナバに付いてきて、さらに深い教えを受けました。「13:43 集会が終わってからも、多くのユダヤ人と神をあがめる改宗者とがついて来たので、二人は彼らと語り合い、神の恵みの下に生き続けるように勧めた。」そして次の安息日には、ほとんど全市をあげてパウロが語る神に言葉を聞きに集まって来たというのです。この町の会堂がどれだけの収容力を持っていたのかわかりませんが、とても全員が入れるほどではないでしょう。会堂を取り巻いて道路に人が溢れている光景が想像できます。当時の状況と現在では事情が違いますが、どうか神の愛と救いを求める人が一人でも多く教会に来ることが出来ますようにと、心から願っております。