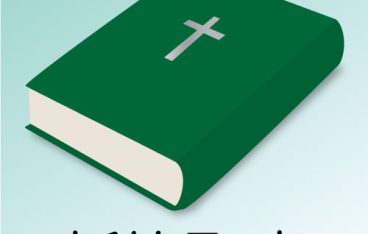2025年9月14日(主日)
主日礼拝『 誕生日祝福 』
使徒言行録 13章44~52節
牧師 常廣 澄子
キプロス島での伝道を終えたパウロたち一行は、その後、海路小アジア地方に向かい、ベルゲに到着しましたが、そこからさらに奥地に向かって、ピシディアのアンティオキアに行きました。この町にはユダヤ人の会堂がありましたから、パウロとバルナバは安息日にその礼拝に参加しました。そしてそこの会堂司から奨励の言葉を語って欲しいと依頼されたパウロは、立ち上がって伝道説教をしたのです。
前回その説教についてお話いたしましたが、その内容は、ユダヤ民族がたどってきた長い歴史から説き起こすものでした。ここでは簡単に短くまとめてあり、出エジプトから語り始めています。イスラエルの民が40年の荒野の旅を経て約束の地カナンに入り、七つの異民族を滅ぼして土地を手に入れたこと、預言者サムエルの時代に、民が王を求めたのでサウルを王位につけたこと、その後ダビデが王になり、このダビデの子孫から救い主が生まれるということが預言されていて、神の救いは初めから神の計画の中にあったこと等を明らかにしていったのです。
パウロの説教はダビデからまっしぐらにイエスに及んでいますが、その際、洗礼者ヨハネ(バプテスマのヨハネ)のことも言及する必要を感じたのでしょう。24-25節の言葉「13:24 ヨハネは、イエスがおいでになる前に、イスラエルの民全体に悔い改めの洗礼を宣べ伝えました。13:25 その生涯を終えようとするとき、ヨハネはこう言いました。『わたしを何者だと思っているのか。わたしは、あなたたちが期待しているような者ではない。その方はわたしの後から来られるが、わたしはその足の履物をお脱がせする値打ちもない。』」が語られています。これは、洗礼者ヨハネのことを真のメシアだと信じる人たちがヨハネの死後もその洗礼運動を続けていたので、ヨハネではなくイエスこそが真の救い主(メシア)であることをはっきり宣言するためであったと考えられます。
そして26節では改めて「兄弟たち、アブラハムの子孫の方々、ならびにあなたがたの中にいて神を畏れる人たち」と人々に呼びかけ、ここからはイエスの死と復活という福音の中心的な内容が語られています。十字架で殺されたイエスは、たしかに敗北者のように見えるかもしれないけれども、実はイエスの死と復活を通して、神がイスラエルの先祖たちに対して約束されていたことが成就したのだということです。パウロは死からの復活という神の力を強調しながら、救い主である神の御子イエスを宣べ伝えていったのです。パウロの論法は聞いている人たちに深い印象を与え、その心に深く食い込んでいきました。まことに巧みでその場にふさわしい適切な語り方でした。
当時会堂にいた人たちは、16節で「イスラエルの人たち、ならびに神を畏れる方々、聞いてください。」と呼びかけられていたように、ユダヤ人もいれば、異邦人であってユダヤ教に改宗した人たちもいれば、まだ改宗はしていないけれども神を礼拝しようと参加している神を畏れ敬う人たちがいたようです。聴衆がどういう人たちであれ、パウロが語った真の救いというものは、神に義とされその救いを受けるのはただイエス・キリストを救い主として信じる信仰によるのだということでした。
パウロの説教を聞いていた人々の反応はどうだったかというと、彼らは深く心を動かされたのです。そして次の安息日にもまた来て同じことを話してくれるように頼みました。また、その日の礼拝が終わった後も大勢の人たちがパウロとバルナバを慕って後に付いてきたのです。二人は彼らに神の恵みの下に生き続けるようにと勧めました。そして次の安息日には、この町のほとんどの住民がパウロが語る神の言葉を聞こうとして集まって来たというのです。「13:44 次の安息日になると、ほとんど町中の人が主の言葉を聞こうとして集まって来た。」
現在残っているこのアンティオキアの遺跡には、大きな劇場や公会堂や競技場の跡が残っており、この町はかなり大きな都市であったことがわかります。(紀元前6年に、ローマ皇帝アウグストがこのアンティオキアをローマの植民都市として、南ガラテヤ州の軍事、政治の中心としています。)しかしこの町の会堂がどれほど大きく立派だったとしても、とても全員が入れるほどの大きさはなかったでしょう。会堂の周囲にたくさんの人が溢れていたのではないでしょうか。町中にどんなに大きな反響が巻き起こっていたかがわかります。
このように、パウロの説教は、大勢のユダヤ人や信心深い改宗者たちや、異邦人たちの間に、イエス・キリストを救い主として信じる信仰に対する好意的な反応を生み出しました。とりわけこの教えは異邦人たちに喜んで受け入れられていきました。パウロの伝道活動に対する実りはたいへん大きかったのです。しかしこれを素直に喜べない人たちがいました。「13:45 しかし、ユダヤ人はこの群衆を見てひどくねたみ、口汚くののしって、パウロの話すことに反対した。」
おそらくこの時に集まって来た町の人たちの多くは異邦人であったと思われます。ところが異邦人が救われることを受け入れられないユダヤ人たちにとっては、パウロの説教も、それが多くの人たちに受け入れられている盛況ぶりも、何もかもいまいましくて我慢ならないことであったのです。
本来ならば自分たちが信じている神が崇められているのですから、その神の言葉を聞こうとしてこんなに多くの異邦人が集まってきていることは大いに喜び感謝すべきことだったはずです。しかし民族的、宗教的偏見を持っていた彼らは、反対に「ひどくねたんだ」というのですから、人間は何と自己中心で情けない心を持っていることでしょう。
彼らはパウロその人を攻撃したというよりも、むしろパウロが宣べ伝えたイエスを口汚くののしったのです。これはパウロとしては何とも我慢できません。自分のことを言われるのであればまだしも、神の言葉に関わることですから、ことは重大です。決然と対応せざるを得ません。そこでパウロたちは言いました。「13:46 そこで、パウロとバルナバは勇敢に語った。『神の言葉は、まずあなたがたに語られるはずでした。だがあなたがたはそれを拒み、自分自身を永遠の命を得るに値しない者にしている。見なさい、わたしたちは異邦人の方に行く。』」もちろん、こう言ったからといって、パウロがユダヤ人伝道を見限ったわけではありません。これ以後もパウロはユダヤ人に福音を語っています。しかし、この出来事が異邦人伝道への契機となったことは疑う余地がありません。神はどんなに不都合なことであろうと、すべてを益とされます。つまりこの出来事が世界宣教への一大転換点となっていったのです。
パウロとバルナバは、さらに続けて言いました。イザヤ書42章6節を引用して、「13:47 主はわたしたちにこう命じておられるからです。『わたしは、あなたを異邦人の光と定めた、あなたが、地の果てにまでも 救いをもたらすために。』」と語り、神の言葉がここに実現していることを宣言したのです。この言葉を語ったイザヤ(第二イザヤ)はあのバビロン捕囚の末期に活動した預言者ですが、「異邦人の光」として地の果てまで救いをもたらす人物の出現を預言しました。それから数世紀を経たこの時、ローマの支配下にあるこの地で、キリストの福音を地の果てまでも届けようとする伝道者が起こされていたのです。
実際、地の果てに住んでいる私たち日本人に対しても、主の福音の種が播かれました。こうして主なる神を信じて、主の日の礼拝に集っている神の民が起こされることを、聖書ははっきり預言しているのです。
「13:48 異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして、永遠の命を得るように定められている人は皆、信仰に入った。」このように、これを聞いていた異邦人たちは喜び、主の言葉を賛美し、信仰に入りました。そして主の言葉はこの地方全体に広まって行きました。しかし、ユダヤ人たちはますます心を硬化させていったのです。
神の言葉はまずユダヤ人に語られなければなりませんでした(13章26節参照)。そのためにここアンティオキアでも、まず救いの言葉はユダヤ人に提供されたのです。しかし、彼らはそれを拒みました。彼らは自らの考えで「自分自身を永遠の命を得るに値しない者にしてしまった」のです(13章46節)。考えてみると、福音を聞くという事は、自分自身の命がどうなるかを決めるという厳粛な岐路に立っているということです。この福音を受け入れるならば、その人は「永遠の命に定められる」のですが、もしこれを受け入れないなら、自分自身に裁きを招くという結果になるのです。
パウロたちが語った福音は、人々の反応をも二分しました。先ず当然ながら、異邦人たちには歓迎され、多くの人たちが救い主イエスを信じました。そして素晴らしいことは、信じた人たちはすぐにアンティオキアの近隣地域や周辺地域に福音を語って行ったことです。「13:49 こうして、主の言葉はその地方全体に広まった。」
反対に、ユダヤ人たちは当然ながら激怒しました。しかし、自分たちの力ではこのパウロとバルナバの二人を追い出すことはできないと判断して、町の上流階級の信心深い貴婦人たちや有力者たちにパウロたちのあることないことを告げて扇動し、迫害してその地方から追い出してしまったのです。ここには、「信心深い貴婦人たち」という言葉が出てきますが、ラムゼイという学者によれば、当時の小アジアの町々では、女性たちがいろいろな公の仕事で、社会的にも政治的にもかなりの地位を占めていたということが報告されています。「13:50 ところが、ユダヤ人は、神をあがめる貴婦人たちや町のおもだった人々を扇動して、パウロとバルナバを迫害させ、その地方から二人を追い出した。」
彼らは、きっと町の住民たちが自分たちユダヤ人を見下したり、自分たちの影響力が後退するのを恐れて、そのような行動をとったのでしょう。彼らは自分たちの評価を気にして見栄や欲のことしか考えることができませんでした。それが神の前にある人間の大きな罪であることに気づくには、どうしたら良いのでしょうか。そこにこそ神への信仰が必要なのです。私たちの信仰は見えるものではなく見えないお方に目を注ぐことです。
パウロとバルナバはユダヤ人たちのこのような反対行動にあって、決意を新たにしました。「見なさい。わたしたちは異邦人の方に行く。」(46節)と宣言し、「13:51 それで、二人は彼らに対して足の塵を払い落とし、イコニオンに行った。」彼らはこの後、アンティオキアを去って南東約130キロのところにあるイコニオンに進んで行きました。
福音が受け入れられずに、人々から反対や反抗を受けた時、抗議のしるしとして、足のちりを払い落すやり方は、主イエスとその弟子たちのやり方でもありました。(マタイによる福音書10章14節、マルコによる福音書6章11節、ルカによる福音書9章5節等参照)
しかし、これを表面的な人間的断絶の意味だけにとるのは危険です。ユダヤ人に対するパウロの態度には、同胞の救いを願う深い愛と思いがあります。ローマの信徒への手紙9章2-3節にパウロの思いが込められています。「9:2 わたしには深い悲しみがあり、わたしの心には絶え間ない痛みがあります。9:3 わたし自身、兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられた者となってもよいとさえ思っています。」
二人の伝道者はこの町を去って行きましたが、彼らが福音を語って、キリスト者となった人たちは、主の弟子となって喜びと聖霊に満たされていました。「13:52 他方、弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。」牧師がいなくなったり、替わったりすると、すぐ内部がガタガタになる現代の教会と違って、彼らには主の霊が伴っていましたから、喜びに満ちていたのです。ピシディアのアンティオキア教会では聖徒らの喜びの賛美があふれ、聖霊による深い交わりが始まりました。そこにはユダヤ人も異邦人もいろいろな文化的背景を持った人たちがいたでしょうが、主を信じるクリスチャンたちの交わりは聖く、主に導かれて、後に主の教会となって行く基盤が形成されていったのです。これは実に喜ばしい神の恵みの業です。
神の御言葉はたしかに信じる者に救いを与えますが、他方、人間に躓きも与えます。これは神の側に不公平があるのではありません。イエスの救いの福音を受け入れるか退けるか、人間は皆その選択と決断の前に立たされていて、何人であれ、その応答は自由なのです。どうか主の救いを受け取る人たちが一人でも多く増えていきますようにと心から祈り願っております。