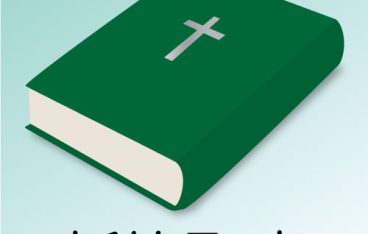2025年9月21日(主日)
主日礼拝『 年長者祝福 』
コリントの信徒への手紙 一 16章13~24節
牧師 常廣 澄子
パウロがコリントの信徒に宛てて書いた長い手紙もようやく最後の結びの部分になりました。普通は結びの挨拶などはさっと読みすごしてしまいがちですが、パウロらしさが十分に現れた大事なところだと思います。ここには事務的な事がいろいろ書かれているのですが、その中にあってまず13-14節では最後の奨励として四つのことが勧められています。「16:13 目を覚ましていなさい。信仰に基づいてしっかり立ちなさい。雄々しく強く生きなさい。16:14 何事も愛をもって行いなさい。」これはコリント教会の人たちだけでなく、現代の私たちにとっても大切なことです。
「目を覚ましている」ことは、コリントのような誘惑の多い町に住んでいる人たちには特に大切なことでした。今、私たちが生きている社会にも人を引き付けて堕落させるような多くの誘惑物が満ちています。また限りなく多くのの情報が氾濫していますから、何が大切であり何が危険なものであるか、私たちは絶えず警戒していなくてはなりません。キリストを信じる者は「信仰に基づいてしっかり立つ」こと、つまりあらゆることをキリストへの信仰に立って判断することが大事なのです。「雄々しく強く生きる」ことは、動揺せずに堂々と生きることです。人の言葉に惑わされたり、おだてに乗って自分の意図しないことをやったりするのは、主を信じる者としては恥ずかしいことだと思います。
ですから、「目を覚まして、信仰に基づいてしっかり立って、雄々しく強く生きる」これらを守ることが大事なのですが、それだけでは足りないものがあります。それは「愛」です。どんなに立派なことであろうと、それを貫く愛がなければ、それはかえって争いを引き起こし、分断を起す原因となってしまいます。ですからパウロは「16:14 何事も愛をもって行いなさい。」と勧めているのです。愛があってはじめて一致があり団結できるからです。
「16:15 兄弟たち、お願いします。あなたがたも知っているように、ステファナの一家は、アカイア州の初穂で、聖なる者たちに対して労を惜しまず世話をしてくれました。」ここに書かれているアカイア州というのは、コリントやアテネなどがある地方の呼び名です。ステファナはこの地方における最初の信仰者だったのです。コリントの信徒への手紙1章16節には、ステファナの家族の人たちに、パウロ自身がバプテスマを施したことが書かれています。福音が受け入れられることが難しいこの土地で、ステファナの一家が信仰者となって行ったことは、パウロにとってどんなに慰めとなったことでしょう。彼の一家はただ信じただけではなく、「聖なる者たちに対して労を惜しまず世話をしてくれました」とあります。教会の中心的役割を担い、こまごまとした雑用をして愛の業に励み、福音伝道のために日夜労してくださったのでしょう。いつの時代でも教会はこのような方々の愛の奉仕によって支えられ、発展してきたのです。
忠実に神に仕えていたのはこのステファナの一家だけではありませんでした。「16:16 どうか、あなたがたもこの人たちや、彼らと一緒に働き、労苦してきたすべての人々に従ってください。」ここを読むと、他にも、彼らと一緒に働いて労苦していた多くの人たちがいたことがわかります。私たちはコリント教会の欠点や悪いところだけを見てはいけないと思います。パウロはこの人たちの働きがわかっていたようで、しっかり認めています。そして彼らを助けようとしています。コリント教会の人たちに、彼らに「従ってください」と要請しているのです。
「16:17 ステファナ、フォルトナト、アカイコが来てくれたので、大変うれしく思っています。この人たちは、あなたがたのいないときに、代わりを務めてくれました。16:18 わたしとあなたがたとを元気づけてくれたのです。このような人たちを重んじてください。」ここに書かれている三人はコリントから来た使者です。この手紙が書かれた時にはパウロがいるエフェソに滞在しています。ステファナ以外の二人がどのような人たちであったかはよくわかっていませんが、わかっているのは彼らがコリント教会の忠実な信徒であったということです。彼らがエフェソにまで来てくれたことは、パウロにとって大変大きな喜びでした。コリントとエフェソは、海を隔ててヨーロッパとアジアにあります。パウロはコリント教会の事をいつも気にして心が動いていましたが、遠く離れているためになかなか思うようにならない悩みがありました。ところが今この三人がコリントから来てくれたのです。コリントから持ってきた手紙と共に、直接コリント教会の様子をいろいろと知らせてくれて、逆にパウロの思いや考えも聞いてくれました。このように顔と顔を会わせて話しをすることで互いに理解し合い、パウロ自身も安心して元気づけられました。ですから、この人たちに対して、コリント教会の人たちは感謝しなくてはならないということを、「このような人たちを重んじてください。」という言葉でパウロは語っています。
ここからはこの手紙を終わるにあたって、いろんな人たちから言付かった挨拶を取り次いでいきます。これは当時の手紙の書き方の一つの慣習でした。「16:19 アジア州の諸教会があなたがたによろしくと言っています。アキラとプリスカが、その家に集まる教会の人々と共に、主においてあなたがたにくれぐれもよろしくとのことです。」ここにある「アジア州の諸教会」というのは、現在のトルコ地域ですが、当時のローマ帝国行政下でのアジア州にあった教会のことです。コロサイの信徒への手紙(4章13-16節参照)を読むと、エフェソ教会の他に、コロサイ、ラオディキア、ヒエラポリス等の教会があったことがわかります。またヨハネの黙示録にある七つの教会も、この頃この地域に起こった教会だと思われます。もちろんそれら全部がパウロの伝道によるものではありませんが、教会と教会が連絡し合って、信仰による友情が交わされていたと考えられます。ここではアジアにある諸教会から、ヨーロッパにあるコリント教会に挨拶が送られています。偶像の神殿があったり、異教文化の根強い地域で、キリストの教会同志が互いに励まし合い、交流することはそれぞれの教会の信徒にとって大きな力となったことでしょう。
「アキラとプリスカ」は、深い信仰の交わりで固く結ばれたご夫妻でした。いろいろなことがあって、パウロがひとり悄然とコリントに来て悪戦苦闘していた時、彼を自分たちの家に迎えて、あたたかくお世話をしてくれたのはこの夫婦でした(使徒言行録18章1-3節参照 ここではプリスキラとなっている)。彼らはパウロと同じように天幕(テント)を造る仕事をしていました。彼らは命がけでパウロの命を守ってくれたと言われています(ローマの信徒への手紙16章3-4節参照)。困難の多いコリント伝道に際して、この夫婦の骨身を惜しまない働きによって、パウロがどれほど慰められ、励まされたことでしょうか。
アキラは、ポントス州出身のユダヤ人で、はじめはローマに住んでいましたが、ユダヤ人追放の命令が出たのでコリントにやってきたのです。そしてこの手紙が書かれた時にはエフェソにいました。やはり伝道を助けるためにパウロと共にこの地に住むようになったのであろうと考えられます。彼らの住んでいる家が教会として用いられ、集会の会場となっていました。この夫婦こそ、初代教会の忠実な信徒の代表格と言っても良いと思います。「アキラとプリスカが、その家に集まる教会の人々と共に、主においてあなたがたにくれぐれもよろしくとのことです。」この挨拶の中にも彼らの信仰と愛が滲み出ていると思います。
「16:20 すべての兄弟があなたがたによろしくと言っています。あなたがたも、聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。」この「すべての兄弟」というのは、今パウロがいるエフェソの信徒たち全員という意味です。このような美しい挨拶を聞いたコリント教会の人たちは、きっとこのように思ったことでしょう。「遠く離れた地にある教会の兄弟たちでさえ、このように自分たちのことを愛と祈りで覚えていてくれる、それに対して、自分たちは分派争いなどをしていてよいであろうか、まずは自分たちの間に愛を持ち、互いに主にある聖い交わりをしていかねばならない。」と。
「あなたがたも、聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。」は、この手紙を読んだ後にはお互い同志、愛の挨拶をしてほしい、という意味です。「聖なる口づけ」というのは、当時の宗教的な愛の表現でした。現在はその習慣は廃れていますが、二世紀頃の教会では集会の際、特に聖餐式の時に、男同志、女同志で互いに口づけをして挨拶していたようです。
この手紙は、パウロが書記の仕事をする人に口述して筆記させています。手紙によっては、筆記した書記の名前をわざわざ書いているのもあります(ローマの信徒への手紙16章22節参照)。ところがこの手紙はだれが書いたのかわかっていません。しかし、一番最後の挨拶だけは、パウロ自身が自分で書いています。「16:21 わたしパウロが、自分の手で挨拶を記します。」これはパウロの署名のようなもので、この手紙全体が、パウロが書いたものであることを証明するためでもありました。
パウロが自ら筆を執って書いた文がこれです。「16:22 主を愛さない者は、神から見捨てられるがいい。マラナ・タ(主よ、来てください)。」ちょっと激しい書き方ですが、これは要するに「主を愛しなさい」ということです。何をするにしてもキリスト者の生活のあらゆる面で、その動機は愛によるものであってほしいということです。その人がどんなに優れた才能を持っていても、主を慕い、主を愛する思いがないならば、その信仰は成長していきません。しかし、ただ主を愛して、主のために仕える気持ちがあるところには、よい知恵が与えられ工夫が生まれ、向上と進歩がついてきます。また教会の中に主を愛する心が満ちているならば、争いや紛争が起こるはずがありません。なぜならば主を愛する者は、その兄弟をも愛するからです。そして主を愛さない者は最後にどうなるでしょうか。その運命について、パウロは大胆に言います。「神から見捨てられるがよい」と。これはつまり滅びです。暗黒の中に見捨てられることです。
そしてここに突然「マラナ・タ(主よ、来てください)」という言葉が出て来ます。これは当時のアラム語がそのまま使われています。その意味は、ここに書かれているように、「我らの主、来てください」という意味です。これはもちろんキリストの再臨のことで、当時の信徒の間では一つの標語か合言葉のように言われていたようです。「主を愛さない者は、神から見捨てられるがいい。」と厳しく言った、そのすぐその後で、「主よ、来てください」と言うことには、この言葉の中に主を愛する心が込められています。原始教会時代は主の再臨を待つ信仰が強く働いていました。主を待ち望むことによって、人々はいつも聖らかに神を愛し、人を愛していくことができたのです。
この手紙の冒頭で(1章3節)「わたしたちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和が、あなたがたにあるように。」と挨拶しましたが、結びの23節でも再び繰り返しています。「16:23 主イエスの恵みが、あなたがたと共にあるように。」主イエスの恵みがあるところには、罪赦された者としての深い平安があります。この主イエスの恵みとは、言うまでもなく、今なお生きてこの世をご支配されている主なる神から来る、私たち人間に対する赦しと慈愛です。
普通パウロの手紙はどれも23節の言葉をもって終わっているのですが、この手紙にはさらにもう一句(24節)が付け加えられています。これはパウロのコリント教会に対する深い配慮だと思います。「16:24 わたしの愛が、キリスト・イエスにおいてあなたがた一同と共にあるように」
考えてみれば、この手紙の中でパウロは、コリント教会の人たちに嫌なこともいろいろ言ってきました。彼らを非難もしました。しかしそれは決して彼らを嫌うとか他意があってのことではありませんでした。彼らのことを思えばこそのことだったのです。本当に彼らを愛していたからこそ、あのような苦言となって現れたのです。ですからパウロは最後に「わたしの愛」と言って、コリント教会の人たちに対する偽りのない愛を率直に語っています。そしてその愛は「キリスト・イエスにある愛」です。キリスト・イエスにあってこそ、愛は純粋となり聖く清らかです。そしてこの愛には力があります。コリント教会の中には複雑な問題がたくさん起こりました。しかしそれらの問題の一つひとつを解きほぐし、解決していく鍵はこのキリストの愛でなければならなかったのです。
パウロの手紙の最後がキリストの愛で結ばれていることは、パウロがひたすらキリストの福音を語り、キリストを指さしていたことにつながり、感動を覚えます。