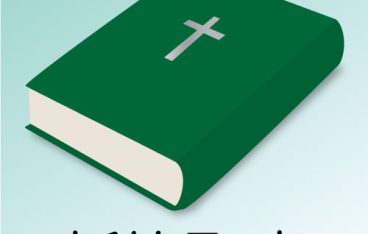2025年10月19日(主日)
主日礼拝
使徒言行録 14章1~20節
牧師 常廣 澄子
私たちは今、使徒言行録を読みながら、パウロとバルナバの伝道の旅をたどっています。ピシディア州のアンティオキアで伝道していたパウロとバルナバは、13章50-51節にあるように、「13:50 ところが、ユダヤ人は、神をあがめる貴婦人たちや町のおもだった人々を扇動して、パウロとバルナバを迫害させ、その地方から二人を追い出した。13:51 それで、二人は彼らに対して足の塵を払い落とし、イコニオンに行った。」迫害を受けてアンティオキアから追われてしまったのです。それでその後、アンティオキアの南東百数十キロメートルの所にあるイコニオンに行きました。
二人はここでも先ずユダヤ人の会堂に行って福音を語りました。「14:1 イコニオンでも同じように、パウロとバルナバはユダヤ人の会堂に入って話をしたが、その結果、大勢のユダヤ人やギリシア人が信仰に入った。」伝道は成功し、大勢の人たちが救い主イエスを信じました。「14:2 ところが、信じようとしないユダヤ人たちは、異邦人を扇動し、兄弟たちに対して悪意を抱かせた。」しかし、二人はこのような反対運動にも屈せず伝道しました。「14:3 それでも、二人はそこに長くとどまり、主を頼みとして勇敢に語った。主は彼らの手を通してしるしと不思議な業を行い、その恵みの言葉を証しされたのである。」ここには「長くとどまり」とありますが、どのくらいの期間かはわかりません。ところが再びイコニオンでも波乱が起きました。「14:4 町の人々は分裂し、ある者はユダヤ人の側に、ある者は使徒の側についた。」ある者はユダヤ人の側につき、ある者は使徒の側に付くというように、町の人達が二派に分裂するという事態が起きてしまったのです。
ピシディア州のアンティオキアでは、「永遠の命を得るに値しない者(13章40節)」と「永遠の命を得るように定められている者(13章48節)」というように、福音の言葉をどう聞くかによって二つに分かれましたが、このイコニオンでは、信仰上の事だけでなく政治的な意味合いがあったのかもしれませんが、ユダヤ人側につくか、使徒側につくかで二派に分かれてしまったのです。
パウロはコリントの信徒への手紙一1章18節で「十字架の言葉は、滅んでいく者にとっては愚かなものですが、わたしたち救われる者には神の力です。」と語っていますが、確かにイエスが語られた福音の言葉は、人を「救い」に導くか、「滅び」に導くか、二つに分けるものであり、それは今も変わっていません。絶対の真理に対しては中立という立場はあり得ないということなのでしょう。それを感謝して受け止めるか、退けるかのどちらかしかないのでしょう。イエスご自身も語っておられます。「だれも、二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。」(マタイによる福音書6章24節)
さて、イコニオンでのパウロとバルナバに対して、ついには「14:5 異邦人とユダヤ人が、指導者と一緒になって二人に乱暴を働き、石を投げつけようとしたとき、14:6 二人はこれに気づいて、リカオニア州の町であるリストラとデルベ、またその近くの地方に難を避けた。」二人は、異邦人とユダヤ人とが指導者と一緒になって自分たちを迫害しようとしているのを知って、リカオニア州の町であるリステラとデルベやその近くに行って難を逃れました。しかしただ難を避けて身の安全のためだけの行動ではありませんでした。逃れて行った先々で福音を語ったのです。「14:7 そして、そこでも福音を告げ知らせていた。」
リストラは、イコニオンから南西約40キロメートルの所にある町です。紀元6年に皇帝アウグストゥスがここを征服したのでローマの植民地となり、軍隊が駐屯していました。このリストラでパウロは、生まれつき足が不自由でまだ一度も歩いたことのない男を癒しました。「14:8 リストラに、足の不自由な男が座っていた。生まれつき足が悪く、まだ一度も歩いたことがなかった。14:9 この人が、パウロの話すのを聞いていた。パウロは彼を見つめ、いやされるのにふさわしい信仰があるのを認め、14:10 『自分の足でまっすぐに立ちなさい』と大声で言った。すると、その人は躍り上がって歩きだした。」
この男の人はパウロの説教に耳を傾けていました。パウロは説教しながら、自分の言葉を一語一語聞き漏らさないようにと熱心に聞いている一人の男に気づいたのです。パウロはこの人をじっと見つめているうちに、彼には神の御言葉を素直に受け取り、癒される信仰があるのがわかりました。そこでパウロは大きな声で「自分の足でまっすぐに立ちなさい」と言ったのです。するとその男の人は躍り上がって歩きだした、というのです。
この癒しの業は、3章にある、エルサレム神殿の「美しい門」でおこなったペトロの癒しの記事とよく似ています。3章ではペトロが男の手を取って立たせましたが、ここでは信仰によって自分で立つように命じています。またペトロによって癒された人は癒しの後で信仰が与えられましたが、ここでは逆で、先に信仰が与えられていた結果、癒されています。
この奇跡はあまりにも衝撃的でしたので、そこにいた人々は非常に驚き、たちまちこの事件は町中を巻き込む大騒動になりました。このリストラがあるリカオニア地方では、普段はギリシア語を話していたようですが、その奇跡があまりに素晴らしい出来事であったため、この地方の言葉であるリカオニアの方言で声を張り上げて叫んだのです。「14:11 群衆はパウロの行ったことを見て声を張り上げ、リカオニアの方言で、『神々が人間の姿をとって、わたしたちのところにお降りになった』と言った。」それだけではなく、年長のバルナバの方が品位もあって風格も備わっていたせいでしょうか、彼をギリシア神話の主神「ゼウス」と呼び、パウロは「おもに話す者」であるという印象を受けたのでしょう、神々の使者、雄弁の神として知られる「ヘルメス」と呼びました。「14:12 そして、バルナバを『ゼウス』と呼び、またおもに話す者であることから、パウロを『ヘルメス』と呼んだ。」
実はこの地方には次のような伝説があったのです。「むかしむかし、このゼウスとヘルメスとがお忍びでこの地方を訪れたことがありました。ところがそうとは知らない町の人たちは皆、この神様たちには無頓着で、誰一人おもてなしする人がいませんでした。その時、ピレモンとバウキスという歳老いた農家の夫婦だけが、この二人の神様たちを招き入れて手厚くもてなしたそうです。そのため、後になってこの老夫婦だけが神の報いを受けました。」というお話です。
そこで、パウロとバルナバのあの驚くべき奇跡を見たリストラの人々は、この二人こそ人間の姿をとったゼウスとヘルメスの再来に違いないと考えたのでしょう。今度こそは失礼のないようにしよう、あの老夫婦に負けないようにしっかりおもてなしをしようというわけで、ゼウス神殿の祭司まで連れて来て、二人にいけにえを献げようとしたのです。「14:13 町の外にあったゼウスの神殿の祭司が、家の門の所まで雄牛数頭と花輪を運んで来て、群衆と一緒になって二人にいけにえを献げようとした。」
真の神を知らないということは、大変な間違いを犯します。リストラの人たちがやったようなことは、科学技術が進んだ現代社会においても、日本でも世界でも、至るところで行われています。人間は、未来のことを予言してそれが実際にそのようになったり、何か人間離れした優れたことをする人が現れると、「現人神(あらひとがみ)」「生き神様」にしてしまうのです。しかし、真の神を知った私たちの信仰の世界では、人間の偶像化は決してあってはならないことです。
しかしこういうことは、今まで読んできた使徒言行録の中にもいろいろありました。カイサリアのコルネリウスが、ヨッパからやって来たペトロを出迎えに出て、「ペトロの足もとにひれ伏して拝んだ」時、ペトロは彼を起して、「お立ちください。わたしもただの人間です(10章25-26節参照)。」と断固として言いました。またヘロデに対して民衆が「神の声だ。人間の声ではない。」と叫び続けるのを制止しようとしなかったため、ヘロデは神に打たれて死にました。(12章22-23節参照)私たちはこれらの出来事をしっかり心に留めておかなくてはなりません。
さて、自分たちがギリシア神話の神々にされそうになっているのがわかったパウロたちは、すぐさま群衆の中に飛び込んで行って、偶像崇拝の愚かさを指摘し、唯一の真の神、万物の創造者にして支配者であられる神に立ち帰るべきことを勧めました。「14:14 使徒たち、すなわちバルナバとパウロはこのことを聞くと、服を裂いて群衆の中へ飛び込んで行き、叫んで 14:15 言った。『皆さん、なぜ、こんなことをするのですか。わたしたちも、あなたがたと同じ人間にすぎません。あなたがたが、このような偶像を離れて、生ける神に立ち帰るように、わたしたちは福音を告げ知らせているのです。この神こそ、天と地と海と、そしてその中にあるすべてのものを造られた方です。』」
そしてパウロは、私たち人間が立ち帰るべき「生ける神」について紹介していきます。第一は「この神こそ、天と地と海と、そしてその中にあるすべてのものを造られた方」だということです。つまり「生ける神」とは、「人間によって造られた神ではなく、人間を含めて天地万物を造られた創造者なる神である」ということです。そのことがわかれば、偶像礼拝という空しいことは捨てることが出来るはずだと訴えています。
神ならざるものを神として崇め敬い、礼拝の対象にすることは、それが人間であれ、動物であれ、物であれ、偶像礼拝であって、生ける神の前では大きな間違いであって罪です。正しい神概念を確立することは、偶像の満ちあふれている世界にあってはとても大事なことです。私たちが住んでいる日本社会には偶像として崇拝されている物がたくさんありますから、そういう環境にある私たちが、天と地と万物を創造した真の神を知ることは大変に難しいことだと思います。
次にこの「生ける神」は真に忍耐強いお方であって、「14:16 神は過ぎ去った時代には、すべての国の人が思い思いの道を行くままにしておかれました。」と語り、真の神の寛容さを伝えています。
そして「14:17 しかし、神は御自分のことを証ししないでおられたわけではありません。恵みをくださり、天からの雨を降らせて実りの季節を与え、食物を施して、あなたがたの心を喜びで満たしてくださっているのです。」というように、この「生ける神」はすべての人に対して平等であり、「恵みの神」であることを紹介しています。
この創造者である「生ける神」がなぜこのように寛容で、しかも恵み深いのかというと、それは人間が空しい偶像礼拝を捨てて、「生ける神」に立ち返るようになるためなのです。そこでパウロは自分たちのことを紹介していきます。私たちは伝道者として「14:15あなたがたが、このような偶像を離れて、生ける神に立ち帰るように、わたしたちは福音を告げ知らせているのです。」と。「14:18 こう言って、二人は、群衆が自分たちにいけにえを献げようとするのを、やっとやめさせることができた。」こうして、人々はやっとパウロもバルナバも自分たちと同じ人間だとわかりました。
このような出来事が起ったリストラでの伝道は、思いがけないことから突然終わりとなります。それは「14:19 ところが、ユダヤ人たちがアンティオキアとイコニオンからやって来て、群衆を抱き込み、パウロに石を投げつけ、死んでしまったものと思って、町の外へ引きずり出した。」何という事でしょうか、前の伝道地であったアンティオキアからは160キロメートル以上離れているにもかかわらず、ユダヤ人たちがパウロとバルナバを追いかけて、アンティオキアとイコニオンからリストラまでやってきたのです。彼らは群衆を抱き込んで、パウロに石を投げつけてその働きを妨害しました。そして死んでしまったものと思って、町の外へ引きずり出しました。それほどに執念深い反対行動が起きていたのです。「14:20 しかし、弟子たちが周りを取り囲むと、パウロは起き上がって町に入って行った。そして翌日、バルナバと一緒にデルベへ向かった。」
石を投げつけられたパウロは気絶してしまったのかもしれません。しかし命は取り留めました。これは奇跡的な神の助けです。彼がもし気を失って「死んでしまった」と思われなかったら、本当に殺されていたかもしれません。パウロが主イエスの救いを伝えようとする熱心さは、命を奪われそうな迫害に遭ってもひるむことなく衰えもしません。敵対するユダヤ人たちは、パウロはてっきり死んでしまったものと思って町の外に引きずり出したのですが、弟子たちが心配そうに周りを取り囲んでいると、むっくり起き上がって立ち上がり、また町の中に入って行ったというのです。パウロの足もとは多少ふらついていたかもしれませんが、その後ろ姿からはすさまじい気迫が感じられたのではないでしょうか。さらに驚くことに、その翌日、パウロはバルナバと一緒に次の宣教地デルベに向かっていったのです。イエスの救いの福音を語るために、このように死と隣り合わせの厳しい旅を続けていったパウロたち一行の熱意と愛とを、私たちは忘れてはならないと思います。