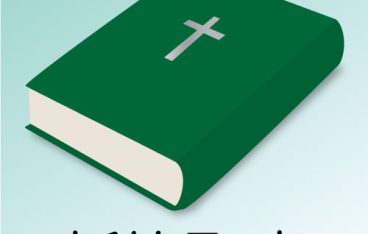2025年11月16日(主日)
主日礼拝『 子ども祝福 』
使徒言行録 14章21~28節
牧師 常廣 澄子
始めに少し前回のところを振り返ってお話ししたいと思います。前回の最後で語りましたように、パウロとバルナバのリストラでの伝道は、思いがけないことが起きて突然終わってしまいました。執念深いユダヤ人たちがパウロとバルナバを追いかけて、160キロメートルも離れているアンティオキアからこのリストラまでやって来たからです。彼らはこの町の群衆を扇動して巻き込み、猛烈な迫害をしました。つい先ほどまで二人を生ける神々として敬い、その前にひれ伏して、バナバをゼウス、パウロをヘルメスと呼んで熱狂的に支持していた人たちがいる、まさにこのリストラの地で事態が急転したのです。人間の心というものは、人の唆しの言葉でこのように簡単に変わるものでしょうか。彼らは彼らを唆したユダヤ人たちと一緒になって、殺意を持ってパウロに石を投げつけました。この場面には、あの「慰めの子」とも言われていたバルナバの姿はありません。キリストの敵対者から回心して、主の福音を語る者となったパウロ一人を目指して激しく石が投げつけられたのです。そして遂に倒れたのを見ると、死んでしまったと思って町の外に引きずりだしたのです(14章19節参照)。死んでしまった人間は卑しく汚れたものとして扱われますから、町の外に運び出さなくてはならなかったのです。
ところで、復活のイエスに出会う前のパウロは、ステファノを石打ちの刑で殺すことに賛成して、皆が上着を脱いで石を投げつけている時、その上着の番をしていたことがありました(7章58節、8章1節参照)。今、パウロはその時のステファノの痛みを味わったのだと思います。しかしこの時のパウロは、以前のパウロではありません。あの時のことを思い出しながら、自分が犯した罪を深く悔い改めて、心から赦しを乞うていたのではないでしょうか。
さてパウロは、ユダヤ人たちや扇動された群衆に激しく石を投げつけられたので、気絶してしまったようです。しかしそれは奇跡的な神の助けでした。もしパウロが気を失って倒れてしまい、人々に「死んでしまった」と思われなかったら、それこそ本当にこの場で殺されていたかもしれません。パウロはだいぶ後になってこの時の体験をこのように語っています。(テモテへの手紙二3章11節)「3:11 アンティオキア、イコニオン、リストラでわたしにふりかかったような迫害と苦難をもいといませんでした。そのような迫害にわたしは耐えました。そして、主がそのすべてからわたしを救い出してくださったのです。」また、コリントの信徒への手紙二11章25節では「鞭で打たれたことが三度、石を投げつけられたことが一度、難船したことが三度、一昼夜海上に漂ったことがありました。」と語っていますが、ここに書かれている「石を投げつけられたことが一度」というのは、このリストラでの体験を指しているのだと思います。
石を投げつけられて打ち殺されるというのは、最も残酷な刑罰です。けれども神はその時、確実に彼に恵みを与えて祝福しました。パウロが後に語っていることから推測すると、この石打ちはパウロに特別な恵みを体験させたのです。コリントの信徒への手紙二12章2-4節を読んでみましょう。そこにはパウロに与えられた恵みの体験が書かれています。「12:1 わたしは誇らずにいられません。誇っても無益ですが、主が見せてくださった事と啓示してくださった事について語りましょう。12:2 わたしは、キリストに結ばれていた一人の人を知っていますが、その人は十四年前、第三の天にまで引き上げられたのです。体のままか、体を離れてかは知りません。神がご存じです。12:3 わたしはそのような人を知っています。体のままか、体を離れてかは知りません。神がご存じです。12:4 彼は楽園にまで引き上げられ、人が口にするのを許されない、言い表しえない言葉を耳にしたのです。」
ここには「14年前に第三の天にまで引き上げられた人」というように、書かれています。この時、パウロは死んだのでしょうか。死んでいなかったのでしょうか。誰も知りません。ある人は、パウロはこの時、一度死んだのだ、そして生き返ったのだと言います。しかしパウロ自身はどうであったか、それを知らないと語っています。たぶんパウロはその時、死んだ人のようになっていたのでしょう。とにかく彼は天に引き上げられて神の栄光を見ることができたのです。ステファノのように石を投げつけられたパウロは、ステファノが見たような神の栄光と神の右に立つイエスを見たのです。「ステファノは聖霊に満たされ、天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、『天が開いて、人の子が神の右に立っておられるのが見える』と言った。」(使徒言行録7章55-56節)私たちは肉体に加えられる痛みや苦しみを恐れます。そういう拷問や迫害に遭ったら耐えられないと思います。しかし、神はその時、神だけが知っておられる栄光を与えてくださるのです。
パウロにとって、イエスの愛とその救いを語ること、つまり主の福音伝道に対する意欲は、自分の命が奪われそうになるほどの迫害に遭っても、ひるんだり衰えることはありませんでした。ましてそれによって伝道することを断念するなどということはあり得なかったのです。この時、気絶したパウロはてっきり死んでしまったと思われて、町の外に放り出されたのですが、弟子たちがパウロの遺体を葬るために周りを取り囲んでいると、パウロはむっくりと起き上がってまたその町の中に入って行ったというのです。死んでしまったと思われた人間が、起き上がったのですから、同行した仲間たちは本当に驚いたことでしょう。そして心から喜び感謝したことでしょう。そして次の日、パウロはバルナバと一緒に次の宣教地であるデルベに向かって出発したのです。まさに奇跡的な出来事です。「14:20 しかし、弟子たちが周りを取り囲むと、パウロは起き上がって町に入って行った。そして翌日、バルナバと一緒にデルベへ向かった。」
デルベというのは、リストラと同じように、リカオニア州にある町です。ここでの活動の記録はわずかですが、この町でも二人は福音を宣べ伝えて、多くの人を弟子にしたのです。何という不屈の伝道精神でしょう。「14:21 二人はこの町で福音を告げ知らせ、多くの人を弟子にしてから、リストラ、イコニオン、アンティオキアへと引き返しながら、14:22 弟子たちを力づけ、『わたしたちが神の国に入るには、多くの苦しみを経なくてはならない』と言って、信仰に踏みとどまるように励ました。」とありますから、この地デルベでは特別な事件は起きなかったようで、神に守られ導かれた伝道であったようです。使徒言行録の20章4節には、パウロの第三回伝道旅行でマケドニア州とギリシアに行ったことが書かれていて、その時の同行者の名前のリストが載っています。「20:4 同行した者は、ピロの子でベレア出身のソパトロ、テサロニケのアリスタルコとセクンド、デルベのガイオ、テモテ、それにアジア州出身のティキコとトロフィモであった。」ここに名前のあるデルベ人ガイオというのは、21節に「二人はこの町で福音を告げ知らせ、多くの人を弟子にして」とあるように、この時にパウロたちから福音を聞いて信仰を持った人だったのでしょう。厳しい伝道旅行の中でも、このような素晴らしい成果があったのです。
それから、パウロとバルナバの二人は、リストラ、イコニオン、アンティオキアというように、今まで伝道して来た道をたどって、弟子たちを力づけながら引き返していきました。これまでにもいろいろな事件が起きた土地ですから、この先、そこでどのような危険な目に遭うかわかりません。しかし恐れることなく、その地の弟子たちを訪れて「わたしたちが神の国に入るには、多くの苦しみを経なくてはならない」と言って励まし、しっかり信仰に踏みとどまるようにと勧めたのです。今日の言葉で言えば、フォローアップであり、アフターケアとも言える行為でありました。信仰を持って歩み始めた者たちにとっては、このような励ましが大きな力になったことと思います。
しかし考えてみると、地理的にはガリラヤ地方の南端のデルベまで来ていたのですから、何もわざわざ危険を冒してまで、迫害を受けたリストラ、イコニオン、アンティオキアへと引き返さなくても、いったん伝道旅行を切り上げて、キリキアの南の山を越えて、パウロの故郷のタルソスを通って、陸路をシリアのアンティオキアに帰ることもできたはずです。しかし彼らはそうしませんでした。彼らにとっては新しく生まれたばかりのクリスチャンたちをそのまま放っておくことはしたくなかったのです。少しでも教え励まして、教会の組織を整え、教会を強めたいと思ったのでしょう。その思いがあえて大変な道を選びとったのです。
また、彼らは伝道してきた町々を再訪しながら、パウロやバルナバがいなくなった後、それらの教会がしっかり神に守られて、その活動や運営が主の御心にそってなされていくようにと、教会毎に長老たちを選んで任命しました。「14:23 また、弟子たちのため教会ごとに長老たちを任命し、断食して祈り、彼らをその信ずる主に任せた。」そしてそのためにパウロたちは断食して祈ったとあります。それほどまでに心にかけるパウロとバルナバの行為からは、後に残していく彼らと主の教会をいかに愛し、心に深く覚えていたかが想像できます。まだ出来上がったばかりの若い小さな教会を思う時、この人たちを残して去らねばならないことを思うと、パウロもバルナバも後ろ髪が引かれるような気持でいたことでしょう。しかし、パウロとバルナバは「彼らをその信じる主に任せた」のです。パウロと言えども、一人で何もかもできるはずがありません。ふさわしい適当な人を選んで任せ、後は神に祈って委ねることしかできなかったのです。しかしこのことは福音伝道、教会形成における大事なことだと思います。
それから二人はピシディア州を通って、パンフィリア州に行き、ペルゲで御言葉を語り、アタリアに下って、船で出発した地アンティオキアに帰って来ました。「14:24 それから、二人はピシディア州を通り、パンフィリア州に至り、 14:25 ペルゲで御言葉を語った後、アタリアに下り、14:26 そこからアンティオキアへ向かって船出した。そこは、二人が今成し遂げた働きのために神の恵みにゆだねられて送り出された所である。」
伝道旅行に出発する時は、パンフィリア州のベルゲで、ヨハネ・マルコが一行から別れてエルサレムに帰ってしまったので(13章13節参照)、このベルゲでは落ち着いて伝道することができませんでした。しかし帰り道の今回はしっかり伝道できたようです。「14:25 ペルゲで御言葉を語った後」と書かれています。それから、ベルゲよりも大きな港町アタリアに下って、そこからシリアのアンティオキアに向かって船に乗りました。
そして無事にシリアのアンティオキアに到着しました。二人は自分たちを送り出してくれたアンティオキアの教会に到着するやいなや教会の人たちを集めて、神が自分たちと共にいて成してくださったこと、行われたすべてのことを語り、多くの異邦人たちに主イエスへの信仰の門が開かれて信じる者がたくさん起こされたことなどをことごとく報告しました。
バルナバとパウロの二人は神に命じられた働きがひとまず終わったことを心から感謝したことでしょう。そしてその後しばらくの間、パウロとバルナバはアンティオキアで弟子たちと共に過ごしたようです。「14:27 到着するとすぐ教会の人々を集めて、神が自分たちと共にいて行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告した。14:28 そして、しばらくの間、弟子たちと共に過ごした。」
本日はバルナバとパウロの伝道の旅の一端をたどりながら、27節に「神が自分たちと共にいて行われたすべてのこと」とありますように、どんな時も神が伴って導いていてくださったことを教えられ感謝いたします。
いまこの世に生きている私たちもまた、ある意味ではこの世を旅している者です。平坦でまっすぐで歩きやすい道もあれば、曲がりくねったでこぼこ道で、危険な所を通ることもあるでしょう。しかし、私たち主を信じる者の人生には、いつもどんな時も主なる神が伴っておられることを信じて、祈りながら希望をもって歩んでいきたいと願っております。私たちを愛して、すべてのことを良き方向へと導かれる主を仰ぎ見て生きていくならば、不安に駆られたり、絶望したりする必要がないからです。
本日は「子ども祝福」の日です。私たちも以前は子どもでしたから、子どもたちが毎日、どんなに明日に、来年に、将来に夢や希望をもって生きているか知っています。子どもたち一人ひとりに命を与え、一人ひとりにその子にしかない良き賜物を与え、その人生を祝福して導かれるのは神です。どうか教会に与えられている子どもたち一人ひとりの上に主なる神が伴っていてくださり、その成長を豊かに育んでくださいますよう、心からお祈りいたします。