コリントの信徒への手紙 一 10章14~22節 牧師 常廣澄子 コリントの信徒への手紙は、コリント教会に生じたいろいろな問題に対して、パウロが主の福音に基づいて適切に解答し、教え導いている実際的な手紙です。この手紙で扱われている問題は多岐にわたりますが、その一つひとつにパウロは率直に答え、指示を与えながら、福音の真理を明らかにしています。まさに福音の伝道者、また牧会者であるパウロの篤い思いがあふれている手紙だと思います。
コリントの信徒への手紙一

46 コリントの信徒への手紙一
主の食卓につく者

46 コリントの信徒への手紙一
永遠に存続するもの
コリントの信徒への手紙 一 13章8~13節 牧師 常廣澄子 先週、私たちはイエス様の復活を喜び、祝い、感謝するイースター礼拝をお捧げいたしました。 本日は、先に天に帰られた方々を偲び、私たちもまたいつの日か神の身許でそれらの方々とお会いする日を思いながら、感謝の礼拝をお捧げしたいと思います。

46 コリントの信徒への手紙一
歴史からの教訓
コリントの信徒への手紙一 10章1~13節 牧師 常廣澄子 イースターを前にして、私たちは今受難節(レント)の時を過ごしています。私たちの救いのために神の御子が十字架に向かって進んでおられるのです。私たちの信じている神は、天の高みにおられてはるか遠くから私たちを見下ろされているような方ではなく、天から降って人間世界に飛び込まれ、ご自分の命さえも捨てることがおできになるお方なのです。そのような愛の神を信じて生きる者がどんなに祝福された者かを、今朝はコリントの信徒への手紙から見ていきたいと思います
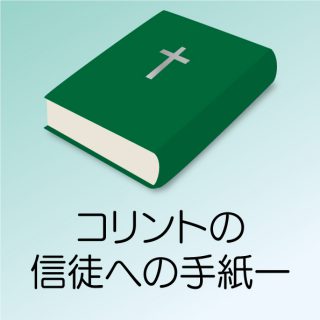
46 コリントの信徒への手紙一
朽ちない冠
コリントの信徒への手紙 一 9章19~27節 牧師 常廣澄子 私たちは今、コリントの信徒への手紙を読み進めていますが、パウロがキリストの福音を自由に語っている姿を見るとほんとうに感動します。パウロが各地を訪問して、あらゆる人たちにキリストの福音を語っているのは、彼の持っている大きな人類愛であったと思いますが、ある意味で、それは自分のような反逆児にさえも現れてくださった復活のイエスに対する感謝の現れです。そして同時に、そのイエスを遣わされた神に対する負い目でもあったのではないでしょうか。ローマの信徒への手紙の1章14節には「わたしは、ギリシア人にも未開の人にも、知恵のある人にもない人にも、果たすべき責任があります。」というように「果たすべき責任」とまで言っています。パウロはキリストの福音を語ることでの様々な苦労を、キリストの十字架の苦しみ、あるいは自分が迫害してきたクリスチャンたちの苦しみに重ねていたのかもしれませんし、何よりもその働きをすることを、神の御前にあって大変光栄なことだと感じていたのではないでしょうか。
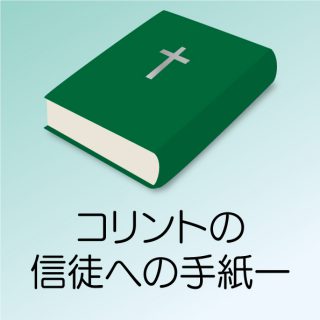
46 コリントの信徒への手紙一
自由にされた者
コリントの信徒への手紙 一 9章1~18節 牧師 常廣澄子 主イエスを信じる人は、自分を愛して受け止めていてくださるお方を知っていて、いつもその守りと導きを信じていますから本当に自由に生きることができます。現に主にあってのびのびと自由に生きておられるたくさんの素晴らしい方々を私は知っています。本日は9章を読んでいきますが、8章では偶像に供えられた肉についてパウロの自由な態度を見てきました。何を食べようと何も問題はないけれども、もし弱い人たちをつまずかせるようなことがあるのであれば、自分は喜んで肉を食べないと宣言したのです。この手紙を書いているパウロは、コリント教会が置かれている厳しく難しい問題を前にしているわけですがとても自由に語っています。自分でもそう言っています。「(1節)わたしは自由な者ではないか。」パウロのこの自由な思いや行動はどこから来るのでしょうか。「風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いても、それがどこから来て、どこへ行くかを知らない。霊から生まれた者も皆そのとおりである。」(ヨハネによる福音書3章8節)の御言葉を思い起こします。パウロの自由というのは、このような主の御霊がなせる業なのだと思います。
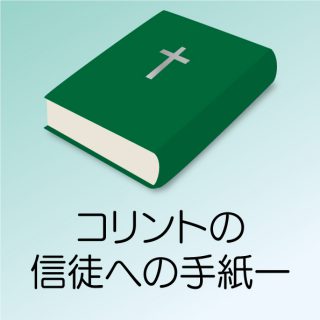
46 コリントの信徒への手紙一
知識と愛
コリントの信徒への手紙一 8章1~13節 牧師 常廣澄子 この個所は、パウロがコリント教会から届けられた質問状に答える形で語っています。まず7章では結婚と独身をめぐる問題について語られていました。それに続いてこの8章では、偶像に供えられた肉を食べてよいかどうかという問題について語っています。これは単に食べるか食べないかということだけではなく、偶像に対してはどのように対応するかという信仰の問題であり、偶像に囲まれて暮らしている私たち日本人キリスト者にとっては実に身近で大切な問題だと思います。この個所は
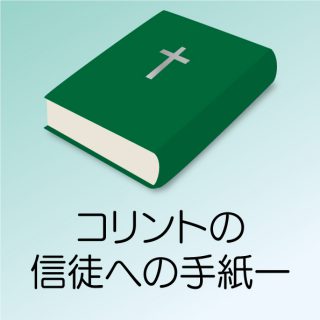
46 コリントの信徒への手紙一
つながれば、生きる
コリントの信徒への手紙一 12章22~27節 シンガポール国際日本語教会牧師 伊藤世里江 聖書:22それどころか、体の中でほかよりも弱く見える部分が、かえって必要なのです。23わたし
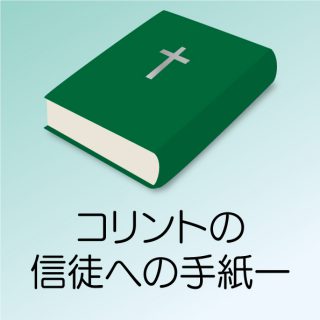
46 コリントの信徒への手紙一
買い取られた者
コリントの信徒への手紙一 7章17~24節 牧師 常廣澄子 コリントの信徒への手紙一の7章には、結婚や離婚という男女の問題や、さらには独
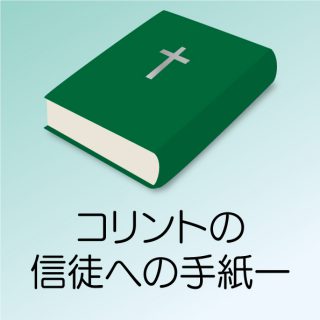
46 コリントの信徒への手紙一
聖霊の住まい
コリントの信徒への手紙一 6章12~20節 牧師 常廣澄子 今までみてきましたように、コリントにあった教会は問題の多い教会でした。先日は教会内の信徒相互の間に起きた問題を、この世の法廷に訴え出たということ訴訟事件についてお話しいたしまし
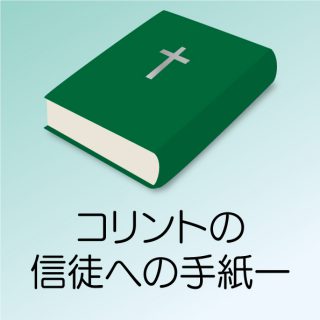
46 コリントの信徒への手紙一
神の国を継ぐ
コリントの信徒への手紙一 6章1~11節 聖書の民であるユダヤ人は、争い事を法廷に持ち出す前に、その地域や会堂の長老に諮って事件を解決していました。この手紙の著者パウロもまた、ユダヤ人として育ち、またファリサイ派のラビから律法を学んでいましたから、人間