エレミヤ書4章1~4節 牧師 常廣 澄子 皆さま、新年明けましておめでとうございます。こうして新しい年を迎えて新年の礼拝ができますことを感謝し、これからの一年もどうか主に助けられ、導かれて歩んで行けますようにと心から願っております。
旧約聖書

24 エレミヤ書
わたしのもとに帰れ

24 エレミヤ書
立ち帰れ
エレミヤ書2章4~9節 牧師 常廣 澄子 エレミヤが生きて活動していたのは、今から2600年くらいも前のことですが、エレミヤに託された主の言葉は、今の私たちにも語られている言葉だと思います。エレミヤはイスラエル王国の最も大変な危機の時代に、主なる神ヤーウェの言葉を文字通り命がけで伝えたのです。

24 エレミヤ書
北から災いが来る
エレミヤ書1章11~19節 牧師 常廣 澄子 前回は、エルサレムの北東にあるアナトトという地で祭司ヒルキヤの子として生まれたエレミヤが、ある時、神から預言者としての召命を受け、以後40年間、神から託された言葉を語るために働いたことをお話ししました。しかしこのエレミヤ書は、エレミヤという偉大な預言者の伝記とか偉人伝のようなものではありません。確かにこの書には、エレミヤが神の言葉を語っていく中で同胞たちから疎まれ、命の危険にさらされ、その心に失意と大きな痛みを抱えながら生きて行ったことが書かれています。ですからエレミヤは「涙の預言者」「悲しみの預言者」とも言われていて、私たちは彼の生涯に引き付けられます。元東大総長の矢内原忠雄は、その著書「余の尊敬する人物」としてあげられている四人の中の一人にエレミヤをあげています。逆境の中でも恐れずに真実を語っていくエレミヤの強さと聖さに惹かれたのかもしれません。しかしエレミヤ書は彼のそういう生涯について書いてあるのでないのです。

24 エレミヤ書
万国の預言者
エレミヤ書1章1~10節 牧師 常廣 澄子 エレミヤは悲しみの預言者、あるいは苦難の預言者と言われています。レンブラントが描いたエレミヤは、左手で頬を支え、洞窟の壁に寄りかかっているのですが、神の言葉を語るという、自分に課せられた預言活動の空しさを思っているのでしょうか、神の言葉に心を留めない傲慢な人間に対しての諦めのようなものが感じられます。システィーナ礼拝堂の天井画には、ミケランジェロが描いたエレミヤの姿があります。ここに描かれたエレミヤは、肩幅広くがっしりしているのですが、右手で顎を抑え、大きな重荷を負わされて何か考え込んでいるかのように見えます。とにかく、エレミヤが預言活動をしていた時代、人々は皆、彼の預言を馬鹿にして無視し、神の言葉をおろそかにしたために遂に国が滅んでしまったのです。

19 詩編
感謝と喜びを持って生きる
詩編 100編1~5節 牧師 常廣澄子 アドベント(待降節)のろうそくが2本灯りました。今私たちは、主の御降誕を待つ喜びの日々を過ごしています。そして本日は「賛美による礼拝」をお捧げしています。有志の皆さまによって「マリヤより生まれたもう」が賛美され、サキソフォーン演奏によって「さやかに星はきらめき」が賛美されました。ありがとうございました。心から感謝いたします。心が高められていく気がします。礼拝堂に賛美の声が満ち溢れ、楽器の音色が賛美の曲を奏でるのを聞いていると、この礼拝はまさに天での礼拝につながっているのだと感じます。

24 エレミヤ書
正義と公義の神様
エレミヤ書 21章8~10節 林 大仁 神学生 涙の預言者、エレミヤは、ユダ王国のヨシヤ王13年の時に預言者としての働きを始め、ヨアハズ王、ヨヤキム王、ヨヤキン王、それから最後の王であるゼデキヤ王に至るまでの40余年を、神を離れ、偶像崇拝の罪を犯し続けるユダ民族へ下される神の正義を預言し、バビロンに降伏することを語り続けた。21章は、いよいよ差し迫ったバビロン王ネブカドネツァルのエルサレム侵攻を前にゼデキヤ王が主の御心を伺おうとエレミヤのところに送った祭司らを前に、エレミヤが改めて神の厳しい裁きを告げる場面である。

12 列王記下
目に見えない現実
列王記下 6章8~17節 宣教師 郭修岩 皆さん、明けましておめでとうございます!神さまからの恵みが豊かな一年となりますように。再び志村教会の礼拝に出席でき、またメッセージを語る機会が与えられることを、心より感謝致します。それと、今まで東京北キリストのために、お祈りとお支えをありがとうございます。まず少し自己紹介をさせていただきます。私は郭 修岩(カク シュウガン)と申します。中国の大連の出身です。2019年からIJCSの派遣宣教師として、東京北キリスト教会で仕えさせていただいています。実は私がシンガポールにいた頃、伊藤世里江先生はメッセージの中でよく志村教会のことを語ってくださいました。先生の志村教会への深い愛情が私によく感じられたのです。一体どのような教会だろうと思いました。前回伊藤先生と一緒に志村教会の礼拝に出席した時、とても歴史があり、信仰熱心、熱意がある教会だと感じられ、とても励まされました。

23 イザヤ書
荒れ野に道を
「(1節)慰めよ、わたしの民を慰めよとあなたたちの神は言われる。」ここでは、神が預言者イザヤに民を「慰めよ」と語っています。「慰める」という言葉の本来の意味は、深く息をすること、深く息を吸い込むことです。この「慰め」は「なぐさみ」ではありません。ただの憂さ晴らしや気を紛らわせて現状に目をつむってしまうことでもありません。聖書で語る「慰める」という言葉には、助けること、贖うこと、憂いの代わりに喜びを与えるという意味が含まれているのです。つまり現状をそのまま受け止める気休めの言葉ではなく、現状を新しく変えていく積極的な言葉だということをしっかり覚えたいと思います。
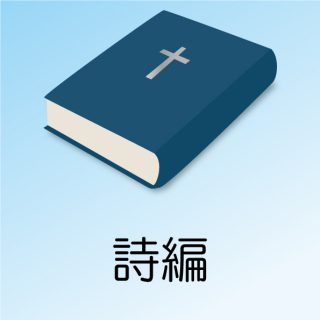
19 詩編
主の慈しみに依り頼む
今朝は詩編のみ言葉から聞いてまいりたいと思います。この詩編143篇は、7つある悔い改めの詩編の最後のものです。いま、この詩人は敵の攻撃によって苦しみの中にいます。その苦境にあって、このような状態から救い出してくださるお方は神以外にはおられないと、ひたすら神の助けを祈り求めているという内容の詩です。

30 アモス書
正義と恵みを求めよ
職業的預言者でも何でもなかった南ユダの国に住む一介の牧者にすぎないアモスが登場して神の言葉を預言したのです。アモスはこの繁栄の陰にある罪を指摘しました。ここでアモスは「主の日」について語っています。「主の日」は神の正義が誰の目にも明らかなものとして示される時です。正義がなされる時には悪は裁かれます。アモスはイスラエルが神の前に悔い改めて生きること、主を求めて生きるようにと勧めているのです。悔い改めて主を求めて生きないならば、必ずイスラエルに主の裁きが臨むのだと語りました。