ルカによる福音書 8章40節~56節 牧師 永田邦夫 本日もまた、ルカによる福音書からのメッセージをご一緒にお聞きして参りましょう。その箇所は、司会者によってお読みいただいた箇所からです。なお、本日箇所は三つ続いている、主イエスさまがなされた奇跡の出来事の最後の段落からです。なお、その奇跡の全体をより深くご理解いただくために、その前後にある記事のことも念頭に置いたうえで、そのメッセージを聞き取っていくと、より幅広くなると思っております。
聖書
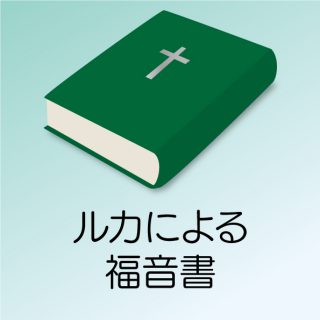
42 ルカによる福音書
少女の蘇生
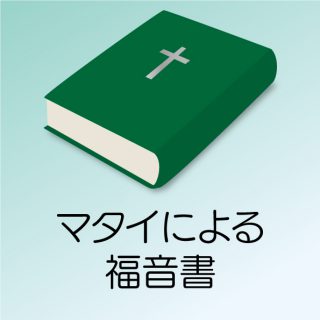
40 マタイによる福音書
自分の命を得る
マタイによる福音書 16章21~28節 牧師 常廣澄子 神の御子イエスは、ユダヤの国で御生涯を送られたのですが、地上で過ごされていた時にいつも御自分が救い主であると自覚して、そのための働きをなさっていたというわけではありません。御生涯の
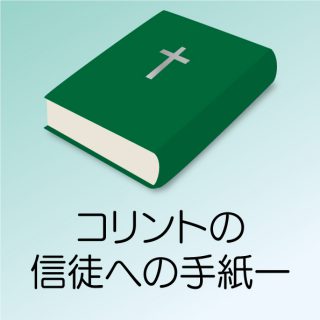
46 コリントの信徒への手紙一
聖霊の住まい
コリントの信徒への手紙一 6章12~20節 牧師 常廣澄子 今までみてきましたように、コリントにあった教会は問題の多い教会でした。先日は教会内の信徒相互の間に起きた問題を、この世の法廷に訴え出たということ訴訟事件についてお話しいたしまし
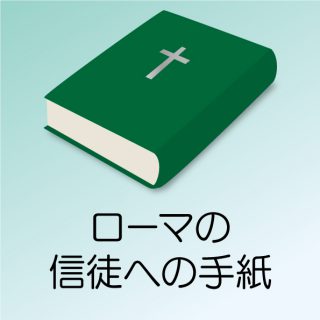
45 ローマの信徒への手紙
心に施された割礼
ローマの信徒への手紙 2章17~29節 牧師 常廣澄子 私たちが今読んでいる聖書は、旧約聖書と新約聖書とを合わせて一つにまとめられていますが、旧約聖書(ヘブライ語聖書)には、律法という人間に対する神の約束ごとがいろいろ書かれています。
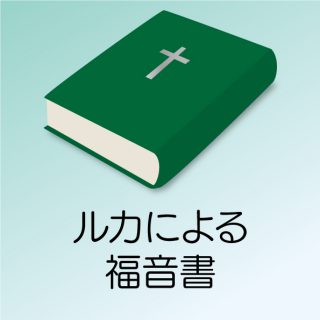
42 ルカによる福音書
レギオンからの解放
ルカによる福音書 8章26節~36節 本日の礼拝は、平和礼拝です。今年は第二次世界大戦の終戦(敗戦)から77年を迎えました。さらに先の8月6日は広島の、そして9日は長崎の原爆記念日でした。これらの記念日は、世界平和を祈り
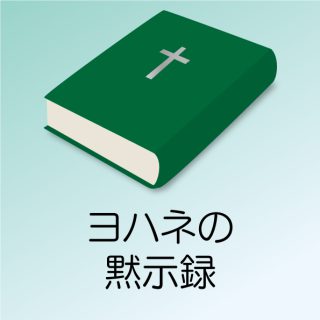
66 ヨハネの黙示録
戸口に立つ方
ヨハネの黙示録 3章14~22節 ヨハネの黙示録には七つの教会に宛てた手紙が収められていますが、今朝の御言葉はその七番目のラオディキアにある教会に宛てた手紙です。エフェソの教会から始まって、一つひとつの教会を使者が訪問してこれらの手紙を届け、その教会の礼拝に出席して手紙を朗読したのだと思います。お気づきのように、これらの手紙はほぼ同じようなパターンで書かれているのですが、似ている所とそうでない所があります。それは、どの手紙にも最初のところに、どういうお方からの手紙かということが書かれているのですが、ラオディキア教会への手紙の冒頭は、大変重々しい表現でイエス・キリストについて表現されています。
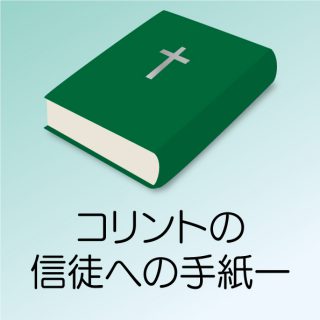
46 コリントの信徒への手紙一
神の国を継ぐ
コリントの信徒への手紙一 6章1~11節 聖書の民であるユダヤ人は、争い事を法廷に持ち出す前に、その地域や会堂の長老に諮って事件を解決していました。この手紙の著者パウロもまた、ユダヤ人として育ち、またファリサイ派のラビから律法を学んでいましたから、人間
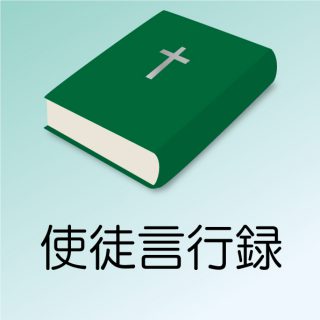
44 使徒言行録
主イエスを信じなさい
使徒言行録 16章25~34節 パウロは大きくまとめて三回の伝道旅行をしました。今の時代に旅行といえば、誰にとっても気分がリフレッシュされる楽しい時ですが、パウロの時代の旅行、しかもイエスの福音を宣べ伝えながらの旅行は決して楽しく楽なものではなかったと思います。今のように便利な交通手段はありませんし、宿泊場所にしても食べ物にしても、どんなに大変で困難な旅だったことでしょうか。また各地を巡りながらの伝道旅行は、パウロが語るキリストの福音を受け入れ、信じて救われる人が起こされる場合もあれば、逆に福音に反対してパウロたちを迫害する人たちもいました。
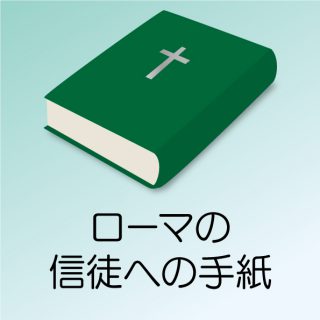
45 ローマの信徒への手紙
正しい裁き
ローマの信徒への手紙2章1~16節 前回は、1章の後半部分から、人間の不義ということについて考えてまいりました。神の存在を無視し、神の御心を離れた人間の心は、羅針盤を失った船のように、どこまでも人間本来の道か
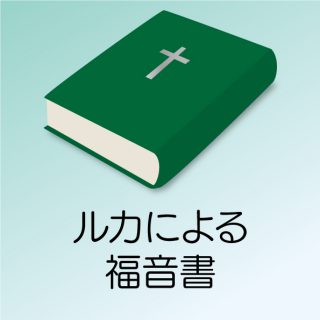
42 ルカによる福音書
種まきのたとえ
ルカによる福音書 8章1節~15節 本日も、ルカによる福音書からのメッセージをご一緒に聞いて参りましょう。その箇所は、8章1節から15節です。「早速、本日箇所に入りましょう」と言いたいところですが、この福音書では、主イエスさまは、その伝道において大きな転換期を迎えようとしておりますので、そのことを先に確認したうえで、本日箇所に入っていきたいと存じます。